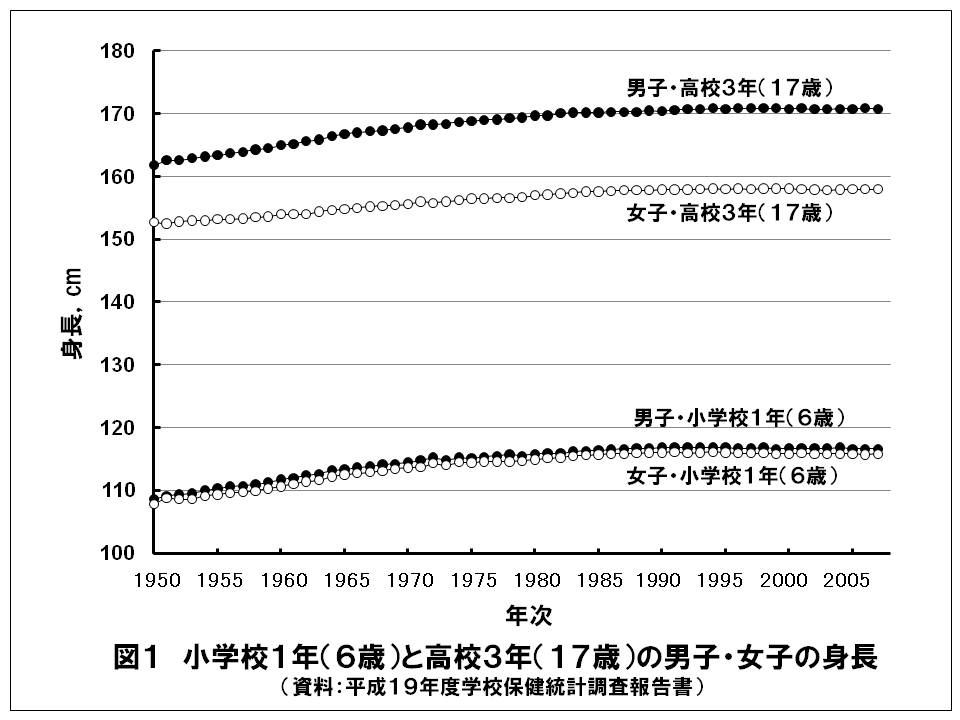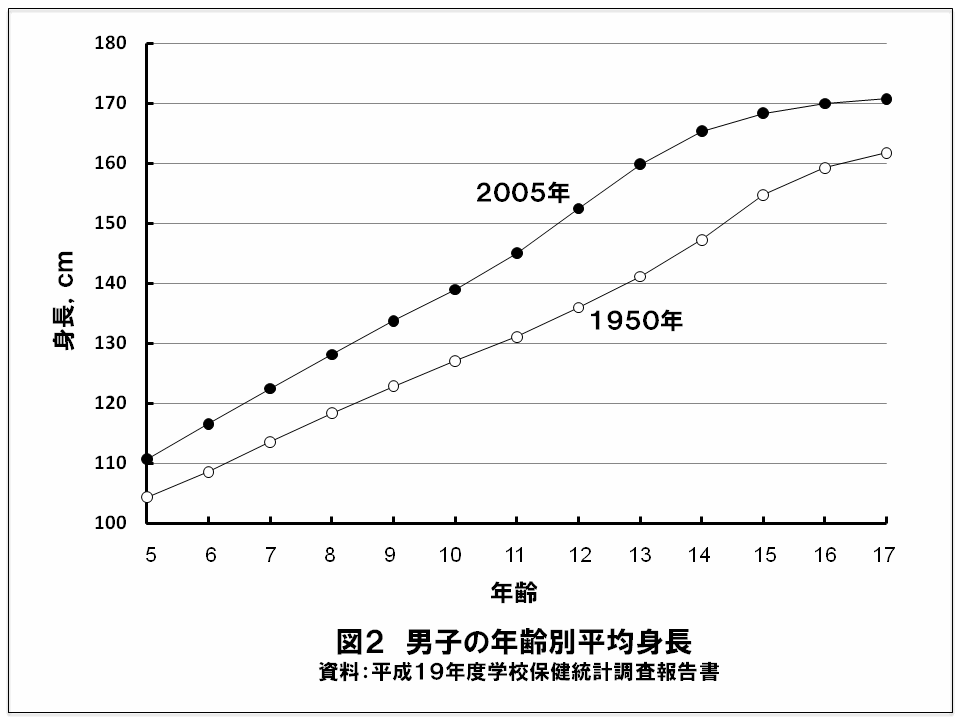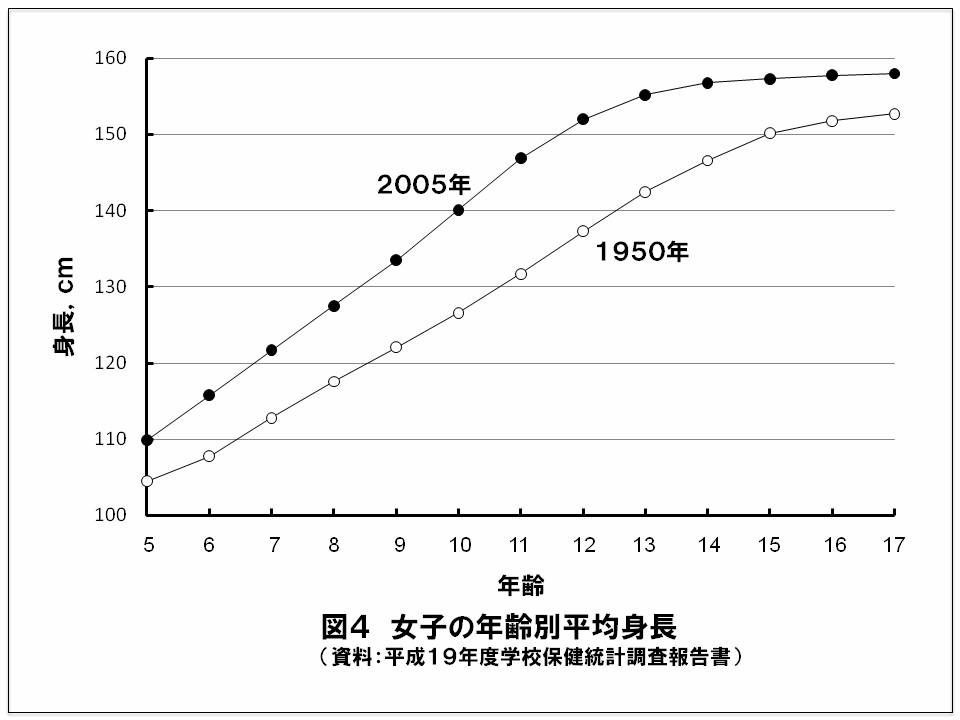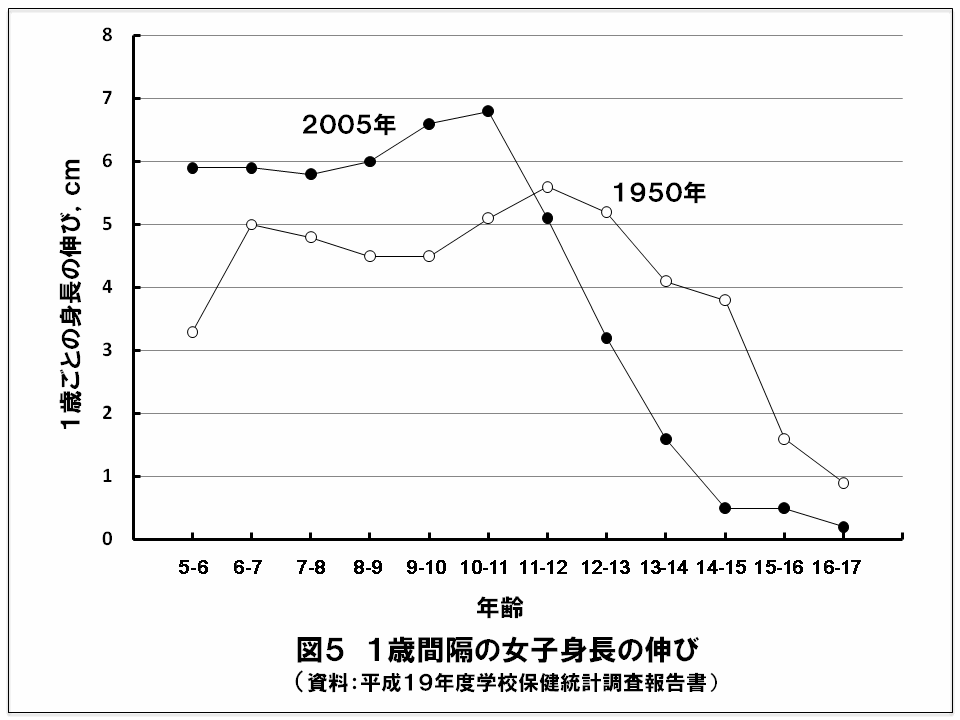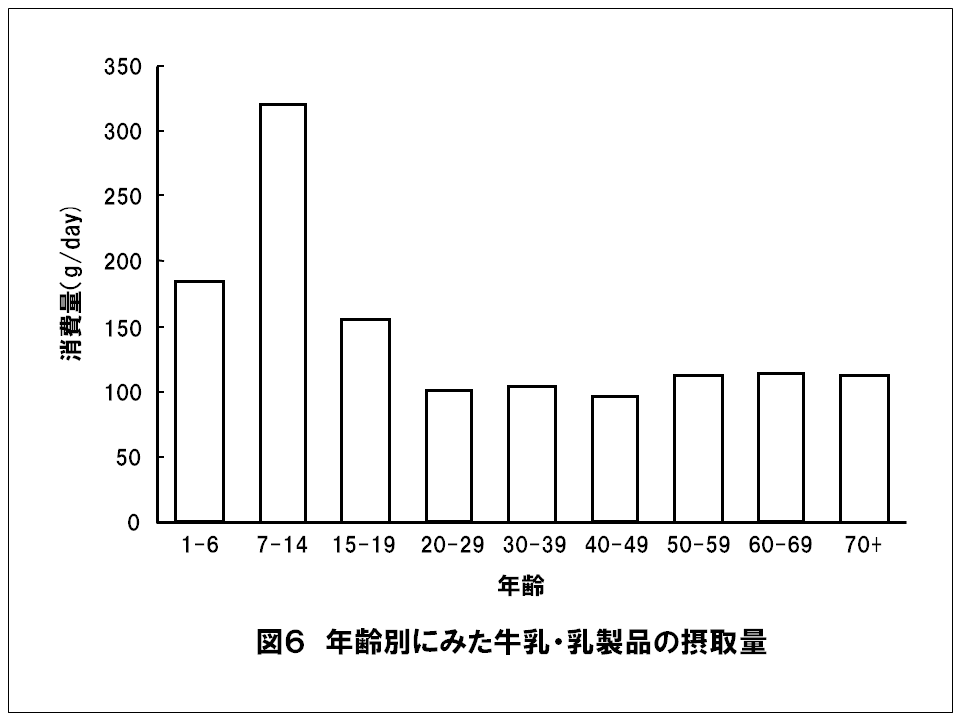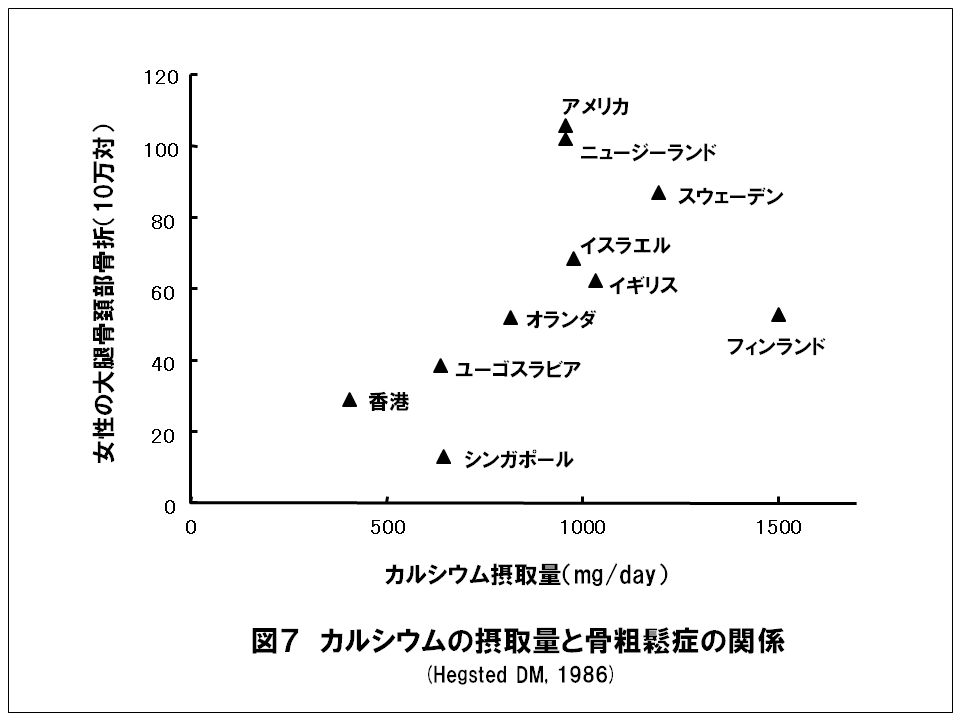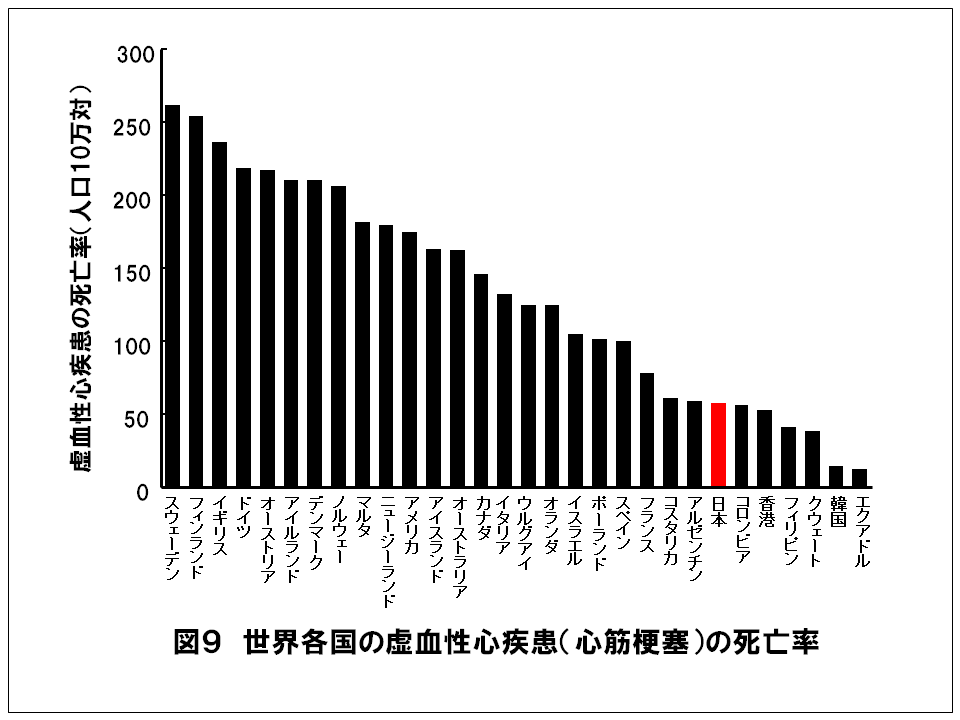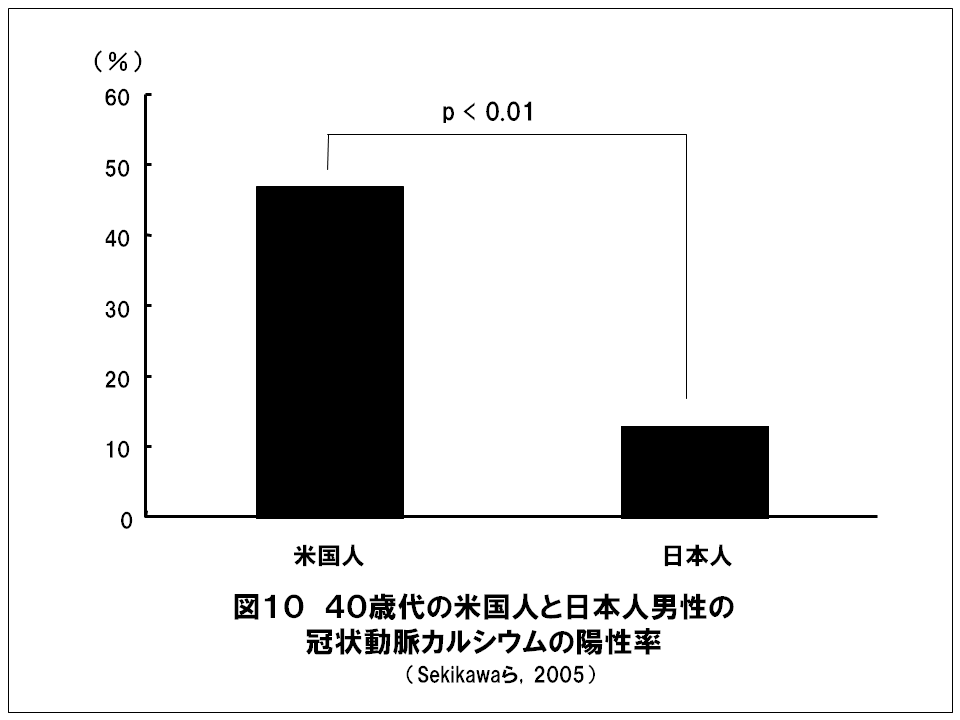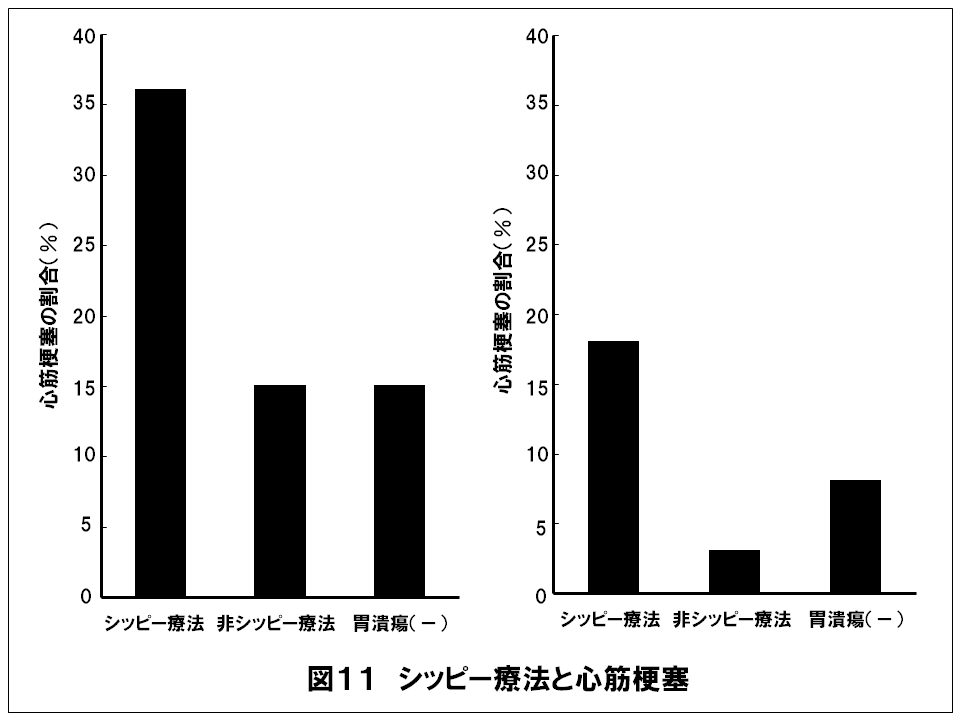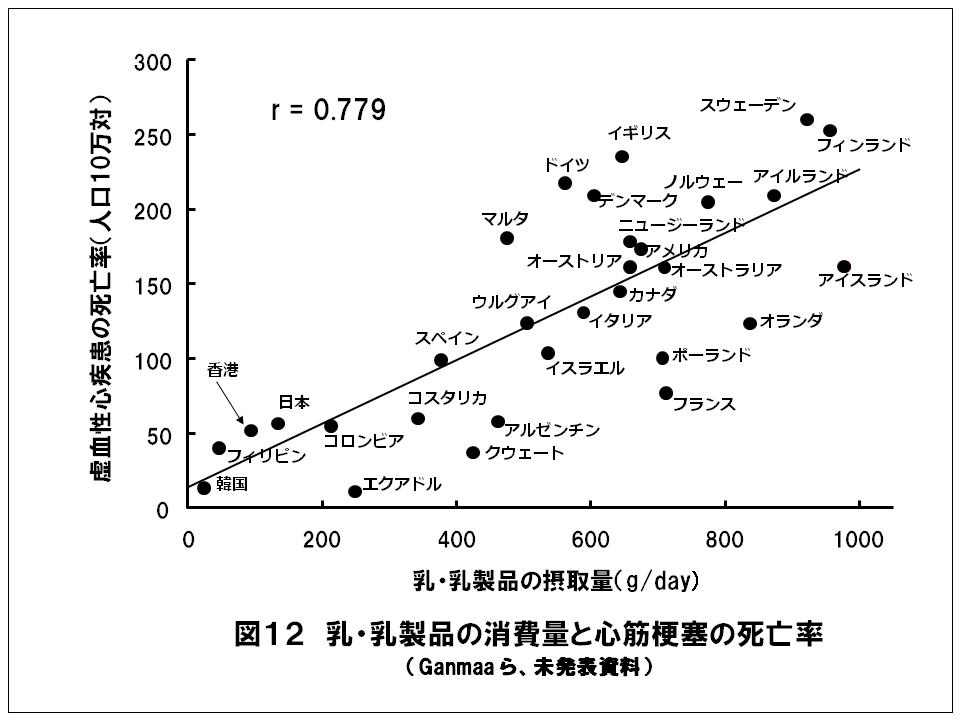牛乳カルシウムの真実
|
1. 日本人にカルシウムが足りないなどということはない! 牛乳は人乳(母乳)に比べて多量のカルシウムとタンパク質を含む。母乳のカルシウムは100g中30mg、タンパク質は1・1gであるが、牛乳は4倍のカルシウム(120mg)と3倍のタンパク質(3・3g)を含んでいる。40〜50kgで生まれたウシは3ヶ月で120〜150kgにもなる。1日に1kgも体重が増える。だから牛乳にはかくも多量のカルシウムとタンパク質が含まれているのである。ひとの赤ちゃんは3kgほどで生まれ12ヶ月でほぼ3倍の約9〜10kgに育つ。ひとの子はウシの子に比べて生長が非常に遅い。牛乳は子ウシの飲みものであって人間の飲みものではないことがお解りいただけるであろう。 日本では、成人一人1日当たり600〜700mgのカルシウム摂取が必要とされている(厚生労働省:カルシウム摂取基準、2005)。2005年の平均カルシウム摂取量は546mgにもなっているが、それでもなお栄養学者は日本人に唯一不足している栄養素はカルシウムであると声高にいう。この「日本人に不足している唯一の栄養素」というキャッチフレーズはもう50年近くも前から叫ばれつづけてきた。この潤沢な日本で、平均値として不足している栄養素などがあるはずがない。栄養学者は何を根拠にカルシウムが不足していると言っているのか。ただ単に「厚労省の摂取基準に比べて少ない」と言ってきたに過ぎない。健康政策を支える栄養学者が「カルシウムが足りない!日本人に足りない栄養素はカルシウムだけ!」と言い続けてきたから、日本人は「足りないのはカルシウムだ!もっとカルシウムを摂らなくては!」と洗脳されてしまった。その背景には牛乳・乳製品を「売らんかな」の商業主義が見え見えである。豆腐のカルシウム含有量を増やすために、牛乳を添加して豆腐を作るという無謀なメーカーすら現れた。 2. 間違っているのはカルシウムの摂取基準 誤っているのは日本人の食生活ではなく、摂取基準である。カルシウムは近年、骨成長(身長)と骨粗鬆症との関連で語られてきた。戦前の日本人の平均カルシウム摂取量は200〜400mgだったと推定される。それでも子どもの歯が生えないなんてことはなかったし、子どもに骨折が多かったわけでもない。骨粗鬆症で骨折などということは稀な事象だった。 骨粗鬆症になると、骨折を起こしやすくなる。高齢者の骨折は「寝たきり」という悲惨な状態を招く。骨折した高齢者の4人に1人は、その骨折から合併症を起こして2年以内に死亡している。カルシウムがこんなに問題になるのは、カルシウムの摂取が少ないと骨粗鬆症になってしまうという宣伝が広まっているからである。栄養学関係者は「牛乳を飲みなさい。さもないと骨粗鬆症になりますよ」と国民の恐怖を煽ってきた。そのためだろう。2005年の60〜69歳のカルシウム摂取量は597mg(男590、女603mg)にもなっている(厚生労働省、平成17年国民健康・栄養調査報告)。 酪農業界にとって、牛乳の唯一の「売り」はカルシウム濃度が高いことである。いずこも同じで、アメリカ酪農評議会(National Dairy Council)は、アメリカ国民が「カルシウムの危機」に瀕しているとして、乳製品の摂取量を増やすよう宣伝を繰り広げている。危機に瀕しているなどとんでもない。アメリカ人のカルシウム摂取量は世界のトップクラスで、その過剰摂取こそ問題である。 官界・学界・業界がこぞって「カルシウムが不足している」と国民を脅迫しなければ、人類が本来必要としない牛乳などを飲む人間がいなくなってしまうのは日本でもアメリカでも同じである。日本人の身体は古来の知恵に支えられている。役所や酪農・乳業界がカルシウム、カルシウムと騒ぎたててもそんな空騒ぎにのらない。日本人は賢明にもカルシウム摂取量をアメリカ人の半分以下にとどめて幾多の病気(乳がん、前立腺がん、心筋梗塞、骨粗鬆症など−後述)を押しとどめている。 カルシウムの摂取量をいくら増やしたところで骨粗鬆症とそれに伴う骨折が予防できるわけではない。ましてや、牛乳の摂取量を増やせば骨折が予防されるなどということはない。酪農・乳業に関係の深いカルシウム栄養学の最大の恥部は「カルシウムは骨の健康に必須だと言っているのに、どうしてカルシウム摂取量の多い国ほど骨粗鬆症や骨折が多いのか」という矛盾を説明できないことにある(後述)。それなのに健康診断を受けると今もって、「骨密度がD判定です。カルシウムが不足していますね。もっと牛乳を飲みましょう」などと言う医師や保健師・栄養士がいる。この人たちはきっと無知(無恥)なのだ。 カルシウムが必須ミネラルであることはいうまでもない。カルシウムはなぜ必要なのか。私たちの身体は体重のおよそ1・2%(700〜800g)のカルシウムを保持しており、その99%は骨に存在する。カルシウムは骨の構造物(柱や梁)を結びつけて強度を与えているセメントの成分だと考えるとよい。残りの1%は血液や細胞の内液と外液に溶けて存在する。細胞の内外に溶けているカルシウムは神経刺激の伝達や心臓の拍動を調節し、細胞機能の調節に重要な役割を果たしている。 カルシウムの血中濃度は8・8〜10・4mg/dlで、細胞内のカルシウム濃度はその1/1000以下に調節されている。つまり、身体の神経伝達や筋肉収縮に必要なカルシウムは極めて微量で、細胞内のカルシウム濃度が高くなれば身体機能が停止してしまう。 骨以外のところに存在するカルシウムは1グラム(1000mg)程度である。それなのに毎日2000mgを越えるカルシウムを摂取しても人間が生きていけるのは、余分なカルシウムがほとんど吸収されないで糞便中に排泄されるからだ。さらに、たとえ吸収されても、余分なカルシウムが速やかに腎臓から尿中に排泄されてしまうからである。 身体の骨は刻一刻と作り替えられている(骨のリモデリング)。骨のカルシウムは絶えずその一部が血液中に溶け出し、新しいカルシウムと置き換わっている(新陳代謝)。子どもの頃(成長期)には骨に入るカルシウムの方が出ていくカルシウムより多いが(骨成長)、50歳を過ぎると骨から出ていくカルシウムが入ってくるカルシウムを上回るようになり、骨は脆くなって折れやすくなる(骨粗鬆症)。この脱カルシウム現象は男ではゆっくり、女では比較的急速に起こる。女性の骨量減少が更年期後に速まるので、エストロジェン分泌の減少を女性の骨粗鬆症の原因と考える研究者が多い。だからといってエストロジェンを補充すれば(ホルモン補充療法;HRT)骨量が増えて骨粗鬆症が予防できるというものではない。HRTの効果は一過性で益より害が多い。 先に述べたように人間の生命維持に必要なカルシウムはごく微量である。成長が停止した大人なら、骨モデリングに使われる分も含めて100mgも吸収されれば生きていくのに支障はない。老人になって大腿骨や背骨が折れて寝たきりになるのは困る。したがって、成人のカルシウム必要量は、毎日どのくらいカルシウムを摂ったら骨折を起こさないかということに注目して基準を定めればよい。 これが基準になるなら、国別のカルシウム摂取量と骨折頻度を調べて、骨折の最も少ない国のカルシウム摂取量を所要摂取量とするのが一番簡単である[1]。世界のカルシウム摂取量を調べてみると、インドの300mg、日本の500mgからフィンランドの1300mgまでさまざまである。前にも述べたが、カルシウム摂取量の多い国(=乳・乳製品の多い国)ほど骨粗鬆症を原因とする骨折が多い。このことは長いこと世界の酪農業界を悩ませてきた。牛乳の最大のセールスポイントが「骨粗鬆症の予防に牛乳を!」だったからである。骨粗鬆症の発生機構は複雑で、単にカルシウム摂取が不足して起こるなどという単純なものではない。骨組織を構成している柱や梁が加齢とともに脆くなり、セメント成分がはがれ落ちていくのが骨粗鬆症である。骨粗鬆症の名だたるイギリス人研究者ケイニス(Kanis JA)は次のように述べる[2]。「骨成長が完了すれば、カルシウム摂取量の増加によって骨格が強くなることはないし、骨折を予防することもない」、「更年期後の女性にカルシウム摂取を奨めて骨折を減らそうという政策に意味はない」と。 3. カルシウムの摂取基準はどのように決められているのか カルシウムの必要量は伝統的にカルシウムの収支バランスで決められてきた[1]。ボランティアにカルシウム含有量の異なる食事を数日から数週間食べてもらい(これで体に入るカルシウム量が判る)、糞便と尿を集めてそれぞれのカルシウムを測定する(体から出るカルシウム量が判る)。[体に入るカルシウム量]と[体から出るカルシウム量]が等しくなるところがゼロバランス(zero calcium balance)である。このゼロバランスがカルシウム必要量とされてきた。ゼロバランスでは体内のカルシウムは増えもしないし減りもしない。しかし、カルシウムなどのミネラルは摂取量が極端に少ないかあるいは極端に多い場合を除くと、身体がその摂取量に適応して毎日の摂取量がゼロバランスになる。つまり、たくさんのカルシウムを摂っている人たちではゼロバランス(=必要量)が高く、摂取量が少ない人たちでは必要量も低いという奇妙なことになっている。アメリカ人のカルシウム必要量が日本人のほぼ2倍になっているのはアメリカ人のカルシウム摂取量(乳・乳製品の消費量に比例する)が多いからである。世界的に眺めると、アジア人・アフリカ人のカルシウム摂取量は欧米人の半分以下である。非欧米人はその少ないカルシウムを効率よく利用して何の不都合もなく生きている。アジア人・アフリカ人は欧米人のように無駄なカルシウムを摂っていないのである。 欧米のようにカルシウムの摂取量の多い(=乳製品の消費量が多い)ところではカルシウムのゼロバランスが高い。無駄遣いするからたくさんのカルシウムが必要なのである。たくさん摂っているから無駄遣いすると言ってもよい。無駄遣いの果てが骨粗鬆症であり心筋梗塞である。カルシウムと心筋梗塞の関係は後述する。 アメリカ酪農業界の「カルシウムが不足している!健康のためにもっとミルクを!」という宣伝にのってアメリカ人のカルシウム摂取量が増えると、科学的?とされるゼロバランスに基づいて勧告されるカルシウム所要量がさらに増える。その結果、骨粗鬆症・骨折で寝たきりになり、心筋梗塞で倒れるアメリカ人が多くなる。アメリカ政府(農務省、USDA)の政策がアメリカ国民を死に追いやっているとは何たる皮肉だろう。いや実は皮肉でもなんでもない。たくさんの人が病気になってたくさんのくすりを服んでもらわないことには自国の経済を維持できないのだ。アメリカ社会はすべてがビジネスである。日本も近ごろそうなった。 4. 生物の適応能力は高い これはすべての栄養素について言えることだが、食うものが乏しければ、人間はその少ない食糧(栄養素)を効率よく使って生き延びるという生物学的能力を備えている。カルシウムが少なければ腸管からの吸収をよくしてカルシウムを余すところなく取り入れ、そのわずかなカルシウムで細胞内カルシウムや骨カルシウムを新しくする。虎の子のカルシウムを尿中にジャブジャブ捨てるなどという無駄をなくす。このことは、岩盤をうがってでも細い根を伸ばして必要な栄養分を取ってくる植物の生命力を思い浮かべれば理解できるだろう。 ビタミンDはカルシウムの体内動態に大きな影響力を発揮する。このビタミンはそのままでは効果がなく、活性型ビタミンD(D3)となってカルシウムの吸収を左右する。カルシウムの摂取量が少ないと、ビタミンD3の生成が増えてカルシウムの吸収率が上がる。これが、アジアやアフリカで摂取量が欧米にくらべて少なくてもカルシウム欠乏が起こらない理由である。環境が許容するカルシウムの摂取量で成長期の子どもや妊娠・授乳中の女性が必要なカルシウムを確保するのは、ビタミンD3がカルシウムを有効に利用するからである。 私たちがどの位のカルシウムを摂ったらよいのか全くわからない。政府がカルシウム摂取基準などという勧告値を定めているのだから、いくらなんでも「全くわからない」ということはないだろうと皆さんはお考えだろうが、実際のところ全くわからないのである。 カルシウムに関してはいくつもの疑問がある。まず第一に、カルシウムや牛乳はいくら摂取しても安全なのか? 栄養の専門家は長いこと、吸収されないカルシウムは糞便中にそのまま排泄されるし、吸収されたが不要のカルシウムは尿中に排泄されるから、いくら摂っても問題ないと考えていた。しかし、牛乳・乳製品からのカルシウムの摂り過ぎは大きな問題を引き起こす(後述)。 5. 牛乳を飲んでも子どもの背は伸びない 最近の日本人は背が高くなったといわれる。国(厚生省と文部省)や業界の「牛乳のカルシウムが骨を丈夫にする」という宣伝が「牛乳を飲むと身長が伸びる」というメッセーッジとなって国民に伝えられたために、親や学校の先生は「牛乳を飲まないと背が伸びない」と嫌がる子どもにも無理やり牛乳を飲ませた。スポーツクラブの監督やコーチは「水を飲むくらいなら牛乳を飲め」と選手を叱咤した。牛乳は子ウシの体重を1日に1kgも増やすほどの飲みものである。ウシの子がこんなに速く成長するのは、大量のタンパク質(母乳の3倍)とカルシウム(母乳の4倍)に加え、強力な成長因子(「牛乳と乳がん」を参照)が牛乳に含まれているからだ。それでは、牛乳は人間の子どもの背も伸ばすのか。 平成19(2007)年度文部科学省「学校保健統計調査報告書」に基づいて、日本の児童・生徒の第二次世界大戦後の身長の推移を眺めてみる。図1は、小学校1年生(6歳)と高校3年生(17歳)の男女の身長が1950(昭和25)年から2005(平成17)年の55年間にどのように変化したかを示したものである。 6歳(小学1年生)男子の身長は、1950年に108・6cmであったが、2005年には116・6cmとなり、55年間で8・0cm伸びた。また、同一期間における17歳(高校3年生)男子の身長の伸びは9・0cmであった(1950年の161・8cmから2005年の170・8cm)。女子の身長はどうか。小学校1年生(6歳)の身長は55年間で8・0cm(107・8→115・8cm)伸び、高校3年生(17歳)の身長は5・3cm伸びた(152・7→158・0cm)。 皆さんは不思議に思われないだろうか。図1を見ると、男女ともに、17歳の身長曲線は6歳の身長曲線をそのまま上方に平行移動しただけのように見える。事実、男子についてみると、1950年には6歳から17歳の間に53・2cm伸びたが、2005年の身長の伸びは54・2cmである。55年間に1・0cmしか大きくなっていない。6歳までの乳幼児の身長の伸び(8.0cm)がほぼそのまま17歳の身長に反映されているに過ぎない。女子にいたっては、1950年の17歳と6歳の身長差は44・9cmであったのに、2005年の差は42・2cmと2・7cmも縮まってしまった。 1950年ごろの子どもは牛乳・乳製品をほとんど口にしなかったが、その55年後の子どもは乳・乳製品の溢れる社会で育った。男女ともに、戦後の55年間で身長が伸びたのは生まれてから小学校に上がるまでの乳幼児の間だけで、その後の前思春期と思春期(6〜17歳)の身長はほとんど伸びていないのである。 1950年の小学校1年生は敗戦の近い1944(昭和19)年の生まれで、食うや食わずの幼少期を過ごした。食うものがなくて大きくなれなかったのである。一方、2005年の小学1年生は、1999(平成11)年生まれで、食うものに困ることのない豊かな時代に育った。2005年の小学校入学生が1950年の新入生に比べて8・0cmも大きくなったのは、牛乳を飲んだからではなく食うものがたっぷりあったからである。何であれ食べるものがたっぷりあれば子どもは大きくなる。 5の1. 牛乳を飲んでも子どもの背は伸びない(男子の場合) 図2に1950年と2005年の男子(5〜17歳)の年齢別平均身長を示した。最近の男の子の身長が最も伸びるのは11〜13歳(ただし、女子は9〜11歳で最も背が伸びる)である。
小学校入学時(6歳)の男子の1950年と2005年の身長差は8・0cmであるが、中学2年(13歳)では18・7cmという非常に大きな身長差となっている。しかし、2005年の子どもは13歳を過ぎると、背があまり伸びなくなり、13歳から17歳にかけての伸びは10・9cmに過ぎない。とくに15〜17歳の高校時代の伸びはわすかに2・4cmである。一方。1950年の13歳の子どもは141・2cmと小さかったが、その後も背が伸び続け、17歳で161・8cmと、13歳から17歳の間に20・6cmも伸びていた(2005年のほぼ2倍)。その結果、17歳男子の1950年と2005年の身長差は9・0cmで、13歳の身長差(18・7cm)の半分以下になっている。換言すれば、最近(2005年)の子どもは13歳ごろまでは身長が急速に高くなるが、その後はこれまた急速に身長が伸びなくなってしまうのである。
このことは男子の身長の伸びを一歳間隔で眺めるともっとよくわかる。図3に1950年と2005年における1歳間隔の男子身長の伸びを示した。最近(2005年)の男子で身長が最もよく伸びるのは11〜12歳と12〜13歳の7・4cmである。その後の身長の伸びは急速に小さくなり、16〜17歳の身長の伸びはわずかに0・8cmと1cmを割り込んでしまう。しかし、1950年には、男子の身長が最も伸びたのは14〜15歳(6・7cm)であった。その後の身長の伸びは小さくなるものの16〜17歳でも2・7cmも伸びていた。最近の小学生・中学生は給食で毎日牛乳を飲まされているが、牛乳を飲んだからといって子どもの最終的な身長が高くなるわけではない。牛乳を飲んでいる最近の男の子は、牛乳を飲まなかった昔に比べて、早く大きくなって早く成長が止まってしまうのである。 最近の男の子の思春期が早まっている。すなわち、早熟(おませ)である。思春期は精巣の発育に最も重要な時期で、男の子の思春期は精巣が大きくなることで始まる。最終的な精子の数を決定する精巣のセルトリ細胞数は思春期に著しく増える[3]。前に「現代牛乳の魔力」で述べたように、市販の乳・乳製品には大量の女性ホルモン(卵胞ホルモンと黄体ホルモン)が含まれている。思春期に取り込まれる牛乳中の女性ホルモンが成人男性の生殖能力(精子数)に与える影響を注意深く見守る必要がある(後述の「牛乳と日本の少子化問題」を参照)。 5の2. 牛乳を飲んでも子どもの背は伸びない(女子の場合) つづいて女子(5〜17歳)の身長の年次推移を見てみよう。男の子と同様に、1950年の女の子は2005年の女の子に比べて身長は低かったが、14歳を過ぎてもなお身長が伸び続けていた(図4)。しかし、最近(2005年)の女子の身長は14歳を過ぎるとほとんど伸びない。1950年に152・7cmであった17歳の女の子の平均身長は55年後の2005年には5・3cm伸びて158・0cmになった。ところが、1950年と2005年における11歳の身長差は15・2cmもある。つまり、小学校入学時(6歳)に8・0cmであった身長差は11歳で15・2cmに広がるが、17歳の身長差は5・3cmに縮まってしまうのである。このことは、最近の女の子の身長は思春期の始まる頃には急速に伸びるが、思春期を過ぎるとほとんど伸びなくなってしまうことを示している。
この現象は、身長の伸びを1歳間隔で示した図5を見ると、さらにはっきりする。昔(1950年)の女の子の身長は14歳から15歳の1年間に平均3・6cmも伸びていたが、最近(2005年)の女子の14歳以後の身長の伸びは年間わずかに0・4cmに過ぎない。 女の子の思春期は乳房の膨らみで始まる。つづいて、性毛が生え、初潮の到来で思春期が終わる。思春期の始まりは身長の伸びが急速に上向く時期に一致する。思春期が終わる(初潮)と、その後の身長の伸びはわずかになる。上で述べたように、かつては14歳を過ぎても身長が伸びていたのに、最近(2005年)の女の子の身長は14歳を過ぎるとほとんど伸びなくなる。最近の女の子の思春期は、1950年頃に比べて1〜2年早く始まり、終了(初潮の到来)が早い。つまり、最近の女の子は、男の子と同様に、昔に比べて早く成長してしまうのである(「牛乳と乳がん」を参照)。
性情報の氾濫する社会環境や夜遅くまで起きているという生活環境が日本の子どもの思春期を早めたという意見もあるが、早熟の一番の理由は、子どもの食べものが戦後の食糧難の時代に比べて格段によくなり、成長が促進されたからである。さらに、1960年ころから摂取量の急増した乳・乳製品中に含まれている女性ホルモンが思春期の到来に与えた影響を無視することはできないだろう。実際、日本人の乳・乳製品の消費量(1人1日当たり)を年齢階級別に見ると、前思春期〜思春期の7〜14歳(307・8g)と幼児期の1〜6歳(221・8g)の消費量が突出している(図6)。因みに、青年期(20〜29歳)の消費量は128・3gに過ぎない。7〜14歳の学童・生徒の乳・乳製品の摂取量がこんなに多いのは、文部省(現・文部科学省)が学校給食法で彼らに牛乳飲用を強制したからである。 6. 牛乳を飲まなくても背は伸びる 2005(平成17)年に定められた日本の男の子に対するカルシウム摂取基準(目標量)は、10〜11歳が800mg、12〜14歳が900mg、15〜17歳が850mgとなっている。少年期の摂取基準がこんなに大きな数値になっているのは、文部科学省が子どもに牛乳を半強制的に飲ませているからである。先に述べたように、必要もないのに毎日多量のカルシウムを摂っていると基準値もそれに応じて高くなってしまうのである。 1950年ごろの日本では食料の絶対量が不足していた。1950年の子どもの身長が低かったのは食べものの絶対量が足りなかったからである。骨の成長にはタンパク質が必要であるが、肉を食べず牛乳を飲まなくても、たっぷりの「穀物+大豆+野菜」の食事で、日本人の身長は遺伝(設計図)の許す範囲で伸びる。背の高い日本人の中には牛乳を好んで飲んだ人もいるだろうが、牛乳が嫌いでほとんど飲まなかったという人もいる。牛乳のカルシウムは身長の伸びと関係ないのである。建築中にいくらセメントを運んだところで、平屋と設計された建物が二階建てになるわけはない。同様に、いくら牛乳を飲んだところで、日本人の平均身長がアメリカ人のように高くなることはない。それなのに、牛乳を飲むと背が高くなると誤って(あるいは故意に)宣伝されてきたのである。 インスリン様成長因子1(IGF-1)が含まれているから、牛乳は乳幼児期に長管骨(四肢の長い骨)を伸長させて思春期の到来を早めるかもしれない。しかし、最終身長は遺伝で決まっているから、思春期の始まりに背が伸びても成長が早く止ってしまうから最終身長は伸びない。さらに、思春期に乳・乳製品あるいはサプリメントで大量のカルシウムを摂取しても、骨量の増加は一時的で後々まで持続しないことは多数の介入研究が証明している[4]。それどころか、思春期に牛乳をたくさん飲むと、牛乳中のエストロジェンによって長骨の成長板(骨端線)が早めに閉じて、かえって身長の伸びが止まってしまうかもしれないのだ。もう一度繰り返すが、牛乳・乳製品は子どもの思春期を早めるだけで、最終的な身長を伸ばすわけではない。 フィンランド人、スウェーデン人、オランダ人などの北欧の人々は多量の乳・乳製品を消費する。古いデータだが、1994〜98年の一人1日当たりの乳・乳製品の消費量を比較すると、フィンランド人の消費量(961・7g)は日本人(186・6g)の約5倍である。乳・乳製品を多く消費している北欧人は背が高い。成人男性の平均身長が日本人の170cmに対して180cmもあると言われている。このことから、乳・乳製品を摂取すると背が伸びるという神話が生まれた。「背が伸びる」は牛乳の最大の「売り」(セールスポイント)であったが、牛乳を飲んでも日本人の背が伸びるわけではないことは上に述べた通りである。 7. 牛乳と骨粗鬆症 ー日本と西洋ー :骨粗鬆症は牛乳をたくさん飲む欧米諸国に多い もう一つの牛乳の売りは「骨を丈夫にし、骨粗鬆症を予防する」である。それでは、乳・乳製品をたくさん摂る西洋人には骨粗鬆症や骨折が少ないだろうか。大方の予想に反して、西洋人は日本人に比べて大腿骨頚部骨折(原因は骨粗鬆症)を起こしやすい[5-9]。例えば、35歳以上の女性の大腿骨頚部骨折の発生率はイギリスのオックスフォードで人口10万対202であるが、鳥取県の同年齢の女性の発生率は半分以下の90である[6]。
カルシウム摂取量の多い国ほど骨粗鬆症が多いというカルシウム・パラドックスを初めて報告したのはハーバード大学のヘグステッド(Hegsted DM)である[7]。彼が取り上げた国は10カ国に過ぎないが、アメリカやニュージーランド、スウェーデンなどのカルシウム摂取量の多い国(=乳・乳製品の消費量が多い国)では、シンガポールや香港などの摂取量の少ない国に比べて大腿骨頚部骨折が非常に多い(図7)。
つづいてアベロウ(Abelow BJ)[8]は、16カ国の動物性タンパク質およびカルシウムの摂取量と50歳以上の女性の骨折発生率との関係を調べた。その結果、カルシウムの摂取量および動物性タンパク質の摂取量と骨折の間に強い正の相関関係が認められた(図8には動物性タンパク質の摂取量と骨粗鬆症の関係を示した)。つまり、肉や乳・乳製品をたくさん摂取している国ほど骨折が多かったのである。アベロウは、カルシウムをたくさん摂取しても、動物性タンパク質の摂取量が多いと酸・塩基平衡が酸性側に傾き、骨のカルシウムが溶け出して尿中に排泄されてしまうから骨粗鬆症になるのだと考えた(これについては再述する)。 イギリスと日本で骨量と骨折(大腿骨頚部骨折)を比較した疫学研究[9]にも触れておく。この研究は、ハートフォードシャーの男172人および女143人と和歌山県太地の男86人および女90人について、体格、骨量(大腿骨頚部と腰椎)、生活習慣(飲酒、喫煙、カルシウム摂取量、屋外活動)などを比較したものである。イギリスでは4年後、日本では3年後に再検査して加齢による骨量変化を比較した。初回測定の骨量は男女ともにイギリス人の方が多かったが、骨量の1年当たりの減少率は男女ともにイギリス人の方が大きかった。つまり、イギリス人の骨量は、日本人に比べて、加齢とともに急速に減少したのである。この傾向はとくにイギリス人女性で顕著にみられた。この調査では、男女とも、体格(BMI)はイギリス人の方が大きく、屋外運動量もイギリス人の方が多かった。体格が大きく、運動量が多いということは骨量減少の予防に役立つことである。それにもかかわらず、加齢に伴う骨量の減少はイギリス人の方がより急速であった。牛乳の飲める西洋人(乳糖分解酵素活性持続症)においても、牛乳は骨粗鬆症を予防できないのである。 牛乳を飲んでも骨粗鬆症の予防にならないことはアメリカで行われた大規模疫学調査[10,11]においても確認されている。そのためアメリカでは、1998年から、「骨粗鬆症の予防に牛乳を」というコマーシャルがメデイアから消えた。日本でも2003年から骨粗鬆症に絡めた牛乳の宣伝が行われなくなったことにお気付きの方もおられるであろう。ただ、日本の場合は理由が明らかでない。5年遅れでアメリカに追随したことになるが、おそらく厚生労働省が酪農業界と乳製品業界に自粛を要請したのだろう。 牛乳を飲まないということはカルシウム摂取量が少ないことと同義に扱われるが、牛乳を飲まない日本人の方が牛乳を多量に飲む欧米人より骨量の減少が少ないというカルシウム・パラドックスをどのように解釈したらよいのだろうか。 8. 牛乳は予防にならないどころか骨粗鬆症をかえって助長する なぜ、牛乳や乳製品のカルシウムが骨粗鬆症の予防にならないのか。前項で、動物性タンパク質・カルシウムの摂取量の多い国ほど骨粗鬆症による骨折が多いというアベロウの研究[8]を紹介した。アベロウはその理由を次のように説明している。牛乳消費量の多い国では牛乳に加えて肉・チーズなどの高タンパク食品の摂取も多い。タンパク質を構成するアミノ酸の中に、メチオニン・システインなどの含硫アミノ酸がある。動物性タンパク質は植物性タンパク質に比べてこれらの含硫アミノ酸を多く含む。含硫アミノ酸は分解されて最終的に硫酸イオンとなり、体液の酸・塩基平衡を酸性側に傾ける。酸性になった体液をアルカリで中和して酸・塩基平衡を保たなければならない。中和に用いられるアルカリ源はカルシウムである。体内のカルシウムの99%は骨に存在する。中和にはもっぱら骨のカルシウムが使われる。実際、動物性であれ植物性であれ、タンパク質の摂取量が増えると尿中に排泄されるカルシウムが増えることは、1970年代に行われた代謝実験でよく知られた事実となっている[12-16]。 アメリカの骨・ミネラル学会は、1997年、「高タンパク食の骨代謝に与える影響」をめぐってシンポジウムを開催した。このシンポジウムで、アルバート・アインシュタイン医学校のバーゼル(Barzel US)とワシントン大学のマッセイ(Massey LK)は「必要以上にタンパク質を摂ると骨量が減る」ことを強調し、骨粗鬆症の予防のためにはタンパク質摂取を少なくし、野菜や果物(ともにカリウムが多い)を多く摂ることを勧めている[17]。一方、クレイトン大学のヒーニー(Heaney RP)は、高タンパク食がカルシウムの尿中喪失を促すことは間違いないが、失われる以上にたくさんのカルシウムを摂れば骨量の減少を防ぐことができると述べた[18]。カルシウム摂取量が少ないときにたくさんのタンパク質を摂ることは問題であるが、摂取量が多ければタンパク質を多く摂っても問題はないというのである。タンパク質摂取量が50gであれば1000mgのカルシウム摂取が必要であり、75gのタンパク質には1500mgのカルシウムが必要というのだ(因みに、ヒーニー氏は全米酪農評議会と国際乳製品協会の医学顧問をつとめ、アメリカとカナダにおけるカルシウム摂取量の勧告案を起草した)。これはとんでもない数値であるが、困ったことに、アメリカの食品・栄養委員会は1997年にこの数値を勧告している(どういう人たちがアメリカのカルシウム摂取基準を定めているのか想像できるだろう)。牛乳はタンパク質が固形成分のほぼ20%を占める高タンパク質食品である(牛乳は水分90%の液体であることを想起してほしい)。今はやりの低脂肪乳はさらにタンパク質の占める割合が増える(脂肪分が2%、1%になれば、タンパク質はそれぞれ25、30%に増える)。 乳糖分解酵素活性持続症(牛乳が飲める)の欧米人でさえ牛乳中のカルシウムは骨粗鬆症の予防に役立たない。役立たないどころか、牛乳は骨粗鬆症を助長しているのだ。まして、牛乳が飲めない(正常である!)日本人が牛乳を飲んでもカルシウムは吸収されない。腸管内の水分だけでなく、腸上皮細胞内の水分も取り込んで、腸管内を下ってしまう。日本人に対する牛乳の効能は便を柔らかくする以上のなにものでもない。 日本人が骨を丈夫に保つ方法はいろいろある。まずは運動である。日光のもとで歩く(自分の体重を運ぶ)などの身体活動で脱カルシウムを予防できる。尿中へのカルシウム排泄を少なくするために、齢をとったらタンパク質の過剰摂取を避けることが重要である。たしかに、骨のモデルチェンジには骨形成細胞(骨芽細胞)が利用できるカルシウムが必要であるが、骨を丈夫に保つには200mgも吸収されれば十分である。多ければ多いほどよいなどというものではないことは当然である。 9. タンパク質の摂り過ぎが骨粗鬆症を招く 1960年以前の日本人のタンパク質の摂取量は少なかった(欧米でも平均的な西洋人のタンパク質摂取量が急増したのは第一次世界大戦後のことである)。タンパク質は生命維持に必須であるが、成長したひとの身体は栄養学者が言うほどには多量のタンパク質を必要としない。19歳から51歳の成人に対するアメリカのタンパク質摂取量の勧告値は0・75g/kgである。これに従うと、体重60kgの人は1日に45gでよいことになる。WHOは成人のタンパク質摂取量は1日当たり0・6g/kgでよいという。60kgの人は36gでよい。日本人の食事摂取基準におけるタンパク質の1日摂取推奨量は50歳以上の男性でなんと60g、女性で55gである。現在の日本人のタンパク質摂取量は総カロリーの16%にも達している。2005年の国民健康・栄養調査によると、60〜69歳の日本人は平均して75・8gものタンパク質を摂取している(うち、動物性タンパク質が40・0gで52・8%を占める)。日本人の身体が悲鳴をあげている。「タンパク質が多すぎる!」 炭水化物*の最終分解産物は炭酸ガスと水であるが、窒素という元素を含むタンパク質は尿素(=タンパク質の主たる最終分解産物)として腎臓から排泄される。人間の腎臓は多量のタンパク質の処理には不向きにできている。日本では現在、慢性腎臓病(CKD)が急増している(日本腎臓学会編、CKD診療ガイド、2007年5月)。2005年の透析患者は25万人を超え、さらに毎年1万人以上も増え続けている。昨今のCKDの急増がタンパク質の過剰摂取によるものかどうか判らないが、ひとたび腎不全になってしまったら、タンパク質摂取を厳しく制限しなければならない[19]。 日本の栄養学は、ドイツ伝来の栄養素栄養学(タンパク質・ビタミン・ミネラルなどの栄養素を強調する栄養学)で、なかでも異常なまでにタンパク質に固執し、常に「タンパク質が足りない」と日本人を洗脳してきた。あらゆる場面で「良質なタンパク質=動物性タンパク質」を推奨してきた。そのせいだろう、今でも「最近、あまり肉を食わないから、スタミナが落ちた」などという若者がいる。いまどき「良質なタンパク質」などという言葉を発する医師・栄養士がいたら、その人は擬(まが)いものである。「良好なタンパク質を!」を唱える医師・栄養士は無知(無恥)であろうが、その背後に商業主義が顔を覗かせている。前にも述べたことだが、肉や乳製品を食べなくても、「穀物+大豆+野菜」で十分量のタンパク質が摂れることを再度強調しておきたい。 もう一度、カルシウムの話題に戻る。牛乳を飲まないで本当に十分量のカルシウムが摂れるのか。この問いには「象を見よ、象は牛乳を飲んでいますか」と答えよう。アフリカ象の巨大な骨格、2メートルにおよぶ立派な牙。あれはみな草や木の葉に含まれているカルシウムから作られたのだ。大地に根を張る植物は土壌のカルシウムを吸収して葉や茎に保有する。陸上の巨大な草食動物はみなこのカルシウムによってあのような巨体になった。 牛乳(=カルシウム)やタンパク質をたくさん摂っている国ほど骨粗鬆症による骨折が多いというカルシウム・パラドックスに対して全米酪農評議会の科学顧問を務めるヒーニー氏はつぎのように反論する[20]。「ヨーロッパ系白人の大腿骨頸部骨折がアジア人に比べて多いのは、股関節の形状が両人種で異なっているからである。ヨーロッパ人の大腿骨は股関節軸(頸部)が長いために解剖学的に折れやすい構造になっている。また、アフリカの黒人はヨーロッパ人よりカルシウムの利用効率に優れており、カルシウム摂取量が少なくても骨の健康度が良好で骨折を起こしにくい。」 つまり、ヒーニー氏は、ヨーロッパ人はカルシウムの利用効率に劣りかつ解剖学的に骨折を起こしやすいのでカルシウムをたくさん摂らなければならないと言うのである。彼の言説に従えば、欧米のカルシウム摂取基準はアジア人にはあてはまらないということになる。 10. 仮説:牛乳・乳製品が心筋梗塞を招く 前述のように、哺乳類は生まれたときの体重がほぼ3倍になるまで母乳で育つように設計されている。だから、3kg強で生まれたひとの子は母乳だけで1年かけて体重が3倍の10kgほどになる。誕生日を過ぎれば母乳を必要としない。ウシは40〜50kgで生まれ、3ヵ月で3倍の120〜150kgに育つ。その後、子ウシは親ウシと同じように草を食って12〜14ヵ月で妊娠可能なほどに育つ。母ウシが子ウシの哺育用に分泌する体液が牛乳である。乳飲みの子ウシは速やかに生長する(1日に1kgも体重が増える!)から、乳液は大量のカルシウムを含む(120mg/100mlで、含有量は母乳のほぼ4倍)。一旦離乳してしまえば、哺乳類は多量のカルシウムを含むミルクを必要としないのである。 2005年の栄養摂取基準で、カルシウム摂取量の目標量(30〜69歳)は1日600mgということになった。この日本の数字はどのように得られているのか。日本でのカルシウム所要量の決め方に触れておく。カルシウムの吸収量([尿中排泄量+経皮的損失量+体内蓄積量])を計算し、これを吸収効率(=[摂取量−糞中排泄量]/[摂取量])で割った数値を必要摂取量としている。しかし、[体内蓄積量]は測定できないから、実際には現実のカルシウム摂取量に約2割を加えた数値が摂取基準となっている。要するに前述のゼロバランス(zero calcium balance)に安全(?)量を加えて必要摂取量を定めているのである。 吸収されたカルシウムの行き先([尿中排泄+経皮的損失+体内蓄積])で、成人で最も大きなのは尿中排泄である。肉や乳製品を大量に食べる欧米人は大量のカルシウムを尿中に排泄することは先に述べた。アメリカ人は毎日およそ200mgのカルシウムを尿中に排泄することでカルシウム平衡を維持している。摂取されたカルシウムの大半は吸収されずに糞中に排泄されるが、たとえ吸収されても尿中に捨てられるだけである。日本の成人のカルシウム摂取量は400〜500mgで十分である。日本人はすでに1日546mgものカルシウムを摂っている(2005年度国民健康・栄養調査)。60代の日本人はなんと597mgも摂っている。「骨粗鬆症の予防のためにカルシウムを摂りましょう(=牛乳を飲みましょう)」という宣伝が行きわたっているためである。高齢者にヨーグルトを勧めるお医者さんや栄養士さんがいる。牛乳を飲めない日本人(腹痛や下痢を起こす)でもヨーグルト(発酵乳)は飲めるからである。昨今の日本人はカルシウムを摂り過ぎる! カルシウムは筋収縮や神経伝達に必須な元素で、その細胞内濃度は血漿中濃度の1/1000に厳密に調整されていることは上述した。血液中のカルシウム濃度も8・6〜10・1mg/dlの一定範囲に調整されている。牛乳を介して大量のカルシウムを日常的に摂取すればどうなるか。たとえ吸収されても、腎臓が余分なカルシウムを尿中に排泄するから、血液中のカルシウムが9mg/dl前後の一定範囲に保たれている(ホメオスタシス)。ところが、この過程で血液中のカルシウムは身体の軟部組織に沈着する。とくに傷ついた組織あるいは異物の付着した組織に沈着しやすい。動脈硬化という傷をもつ血管は、カルシウム沈着の格好の標的となる。血液中にあふれるカルシウムはとくに血管内膜へのコレステロールなどの侵入によって形成される肥厚斑(プラーク)の周辺部に好んで沈着する。心臓を養う血管(冠動脈)のプラークにさらなるカルシウム沈着が起こって次第に管腔が狭まる[21]。これが虚血性心疾患の始まりである。冠動脈の血流が途絶えると心筋梗塞を起こす。 骨粗鬆症の多い国々(欧米)では心筋梗塞が多い。骨粗鬆症の女性は心筋梗塞になりやすいことが知られている[22]。骨粗鬆症と心筋梗塞を結びつけているのは動物性食品(獣肉と乳・乳製品)である。骨から離脱したカルシウムが冠動脈に沈着して高度の冠動脈硬化を起こすからである。 カルシウムがいかに沈着しやすい元素であるかは、歯石を例にとればわかりやすい。みなさんの中には歯周病の予防のために半年に一回は歯科医院に歯石をとってもらっている方がいらっしゃるだろう。あの歯石は磨き残した食べ物のカスに細菌が巣くって生じた歯垢に唾液中のカルシウムが沈着してできる石のように硬い付着物である。普通の歯ブラシで取り除くことはできない。毎日歯を磨きつづけても歯石は少しずつ増える。歯石の表面は凹凸しているからさらにここに歯垢がたまり、歯肉を刺激して歯周病を誘発・悪化させる。
国際的に眺めると、日本人に比べて、欧米では圧倒的に多数の人々が虚血性心疾患(心筋梗塞)で死亡している。国連人口統計年鑑(Demographic Yearbook 2000)によると、虚血性心疾患の死亡率(人口10万対)は日本で56・9(1997年)であるが、最も高いスウェーデンは260・8(1996年)、第二位のフィンランドは253・1(1996年)、次いでイギリスの235・5(1998年)、ドイツの217・9(1998年)と続いている(図9)。アメリカの死亡率173・9(1997年)は北欧諸国の死亡率より低いが、それでも日本の3倍を超えている。なぜ、欧米にはこんなに心筋梗塞が多いのだろうか。 アメリカには心筋梗塞が多い。アメリカの若者には冠動脈硬化が高率に発生する。今でも語り継がれている有名な話に、朝鮮戦争で戦死したアメリカ軍兵士の剖検報告がある[23,24]。若い韓国兵には皆無であったが、アメリカ兵戦死者300名(平均年齢22歳)の77%に何らかの動脈硬化の病変がみられ、39%にプラーク(内膜の斑状肥厚性病変)による冠動脈の狭窄がみられた。戦争という極限状態にあった兵士の剖検記録であるから多少割り引いて考えなければならないが、アメリカ軍兵士の幼いころからの食事が冠動脈の硬化をもたらしたと考えられる。 最近、冠動脈硬化・心筋梗塞の診断と予後判定に有効な手段としてEBCT(Electron-Beam Computed Tomography;電子ビームコンピュータ断層撮影)が用いられるようになった[25]。心筋梗塞がアメリカほど深刻ではないこともあってか、日本ではEBCTによる冠動脈石灰化のスクリーニングはあまり行われなかったが、最近は注目されるようになっている[26]。
40歳代の日本人男性100名と、同じく40歳代のアメリカ人男性100名の冠状動脈へのカルシウム沈着を測定した報告がある[27]。これによると、冠動脈硬化・心筋梗塞の危険因子とされる血圧・総コレステロール・LDL-コレステロール(悪玉コレステロール)・血糖値・喫煙率はすべて日本人の方がアメリカ人より高いのに、日本人の冠動脈の石灰化はアメリカ人よりはるかに低かった(図10)。どうして、日本人とアメリカ人でこんなに違うのか。私は、日本とアメリカで乳・乳製品の摂取量(=カルシウム摂取量)が大きく異なるからであると考えている。しかし、この研究の報告者は、虚血性心疾患による日本人の死亡がアメリカ人よりずっと少ないのは、日本人がn-3系脂肪酸(EPA、DHAなど)を多量に含む魚介類をたくさん食べるからだと推論し、カルシウム摂取量の差異には一顧だにしない[28]。この方々は、まさか、カルシウムのような優れたミネラルが心臓に悪さをしているなどとは思いもしなかったのだろう。 かつて、胃潰瘍の治療に、アメリカの内科医シッピー(Sippy BW)が考案した、患者に大量の牛乳を飲ませるというシッピー療法が用いられたことがある。胃酸を中和するために重炭酸ソーダを飲ませ、2時間後から牛乳と乳脂の混合液を摂取させるというものであった。牛乳が保護膜を作って胃壁を守ると考えたのである。1950年代に、このシッピー療法を受けた胃潰瘍患者に心筋梗塞が多発することが問題になった。ブリッグス(Briggs RD)[29]はアメリカとイギリスの病院における1940〜1959年の剖検記録から胃潰瘍でシッピー療法を受けたことのある剖検例(アメリカで97例、イギリスで95例)、胃潰瘍になったがシッピー療法を受けなかった剖検例(アメリカで97例、イギリスで95例)を集めて、シッピー療法と心筋梗塞の関係を調査した。同時に、それぞれの国で、胃潰瘍でない患者の剖検記録から年齢、人種、死亡時期の近い症例を胃潰瘍症例と同数(アメリカ194例、イギリス190例)選び出して対照群とした。
その結果、アメリカでシッピー療法を受けた胃潰瘍患者(97例)のうち35例(36%)が心筋梗塞で死亡したが、シッピー療法を受けなかった胃潰瘍患者(97例)に発生した心筋梗塞は15例(15%)で、シッピー療法を受けた患者には明らかに心筋梗塞が高率に発生していた(図11左)。イギリスでも同様で、シッピー療法を受けた胃潰瘍患者(97例)では17例(18%)に心筋梗塞が発生し、シッピー療法を受けなかった胃潰瘍患者(97例)に発生した心筋梗塞は3例(3%)に過ぎなかった(図11右)。 この調査結果が報告されてから、胃潰瘍に対するシッピー療法は行われなくなった。当時(1960年代)は牛乳・クリームで心筋梗塞が起こるのは牛乳やクリームに含まれている乳脂肪(飽和脂肪)が冠動脈に動脈硬化を起こすことが原因であると考えられていた。上で述べてきた話を総合すると、牛乳中の飽和脂肪はたしかに肥厚性病変(プラーク)の形成に一役買っていたであろうが、この病変にカルシウムが沈着して高度のプラークとなり、心筋梗塞を起こしたと考えるのが妥当である。
乳・乳製品を多量に摂取するスウェーデン、フィンランド、ノルウェイ、デンマークなどの北欧諸国は虚血性心疾患の死亡率が高い。先に掲げた「世界各国の虚血性心疾患(心筋梗塞)の死亡率(図9)」に収載されている30ヵ国の虚血性心疾患の死亡率と牛乳・乳製品の摂取量の間には高度の相関関係(r=0・78)が認められる(図12)[30]。近年は増えているが、欧米人に比べると日本人の乳・乳製品の消費量は少ない。したがって、今後とも、日本の心筋梗塞が欧米並にになることはないだろう。しかし、日本では脳梗塞が増えている。日本人の動脈硬化は冠動脈よりも脳動脈に発生しやすい。日本人の脳動脈硬化の最大の危険因子は高血圧であるが、カルシウムの沈着もこの硬化の増悪に一役買っているのかもしれない。 文献 2. Kanis JA. The use of calcium in the management of osteoporosis. Bone 24: 279-290, 1999. 3. Sharpe RM, McKinnell C, Kivlin C, Fisher JS. Proliferation and functional maturation of Sertoli cells, and their relevance to disorders of testis function in adulthood. Reproduction 125: 769-84, 2003. 4. Lanou AJ, Berkow SE, Barnard ND. Calcium, Dairy Products, and Bone Health in Children and Young Adults: A Reevaluation of the Evidence. Pediatrics 115:736-743, 2005. 5. Ross PD, Norimatsu H, Davis JW, Yano K, Wasnich RD, Fujiwara S, Hosoda Y, Melton LJ 3rd. A comparison of hip fracture incidence among native Japanese, Japanese Americans, and American Caucasians. American Journal of Epidemiology 133 :801-809, 1991. 6. Yamamoto K, Nakamura T, Kishimoto H, Hagino H, Nose T. Risk factors for hip fracture in elderly Japanese women in Tottori Prefecture, Japan. Osteoporosis International 3 (Suppl 1):48-50, 1993. 7. Hegsted DM. Calcium and osteoporosis. Journal of Nutrrition 116: 2316-2319, 1986. 8. Abelow BJ, Holford TR, Insogna KL. Cross-cultural association between dietary animal protein and hip fracture: a hypothesis. Calcified Tissue International 50: 14-18, 1992. 9. Dennison E, Yoshimura N, Hashimoto T, Cooper C. Bone loss in Great Britain and Japan: a comparative longitudinal study. Bone 23:379-82, 1998. 10. Owusu W, Willett WC, Feskanixh D, Ascherio A, Spiegelman D, Colditz GA. Calcium intake and the incidence of forearm and hip fractures among men. Journal of Nutrition 127: 1782-1787, 1997. 11. Feskanich D, Willett WC, Stampfer MJ, Golditz GA. Milk, dietary calcium and bone fractures in women: a 12-year prospective study. American Journal of Public Health 87: 992-997, 1997. 12. Walker RM, Linkswiler HM. Calcium retention in the adult human male as affected by protein intake. Journal of Nutrition 102: 1297-1302, 1972. 13. Schwartz R, Woodcock NA, Blakely JD, MacKellar I. Metabolic responses of adolescent boys to two levels of dietary magnesium and protein. II. Effect of magnesium and and protein level on calcium balance. American Journal of Clinical Nutrition 26: 519-523, 1973. 14. Anand CR, Linkswiler HM. Effect of protein intake on calcium balance of young men given 500 mg calcium daily. Journal of Nutrition 104: 695-700, 1974. 15. Margen S, Chu JY, Kaufmann NA, Calloway DH. Studies in calcium metabolism. I. The calciuretic effect of dietary protein. American Journal of Clinical Nutrition 27: 584-589, 1974. 16. Chu JY, Margen S, Costa FM. Studies in calcium metabolism. II. Effects of low calcium and variable protein intake on human calcium metabolism. American Journal of Clinical Nutrition 28: 1028-1035, 1975. 17. Barzel US, Massey LK. Excess dietary protein can adversely affect bone. Journal of Nutrition 128: 1051-1053, 1998. 18. Heaney RP. Excess dietary protein may not adversely affect bone. Journal of Nutrition. 128: 1054-1057, 1998. 19. Ideura T, Shimazui M, Morita H, Yoshimura A. Protein intake of more than 0.5 g/kg BW/day is not effective in suppressing the progression of chronic renal failure. Contrib Nephrol 155:40-49, 2007. 20. Heaney RP. Calcium, dairy products and osteioporosis. Joural of American College of Nutrition 2000; 19: 83S-99S. 21. Schmermund A, Molenkamp S, Erbel R. Coronary artery calcium and its relationship to coronary artery disease. Cardiology Clinics 71: 521-534, 2003. 22. Tanko LB, Christiancen C, Cox DA, Geiger MJ, McNabb MA, Cummings SR. Relationship between osteoporosis and cardiovascular disease in postmenopausal woman. Journal of Bone and Mineral Research 20: 1912-1920, 2005. 23. Enos WF, Holmes RH, Beyer J. Coronary disease among United States soldiers killed in action in Korea; preliminary report. Journal of American Medical Association 152: 1090-1093, 1953. 24. Enos WF Jr, Beyer JC, Holmes RH. Pathogenesis of coronary disease in American soldiers killed in Korea. Journal of American Medical Association 158: 912-914, 1955. 25. O'Rourke RA, Brundage BH, Froelicher VF, et al. American College of Cardiology/American Heart Association Expert Consensus document on electron-beam computed tomography for the diagnosis and prognosis of coronary artery disease. Joirnal of American College of Cardiology 36: 326-340, 2000. 26. 関川暁、岡村智教、門脇崇、他.潜在的動脈硬化所見の早期発見とその公衆衛生学的意義.米国における電子ビームコンピュータ断層撮影を用いた虚血性心疾患初回発症予防の取り組み.日本公衆衛生学雑誌 2003; 50: 183-93. 27. Sekikawa A, Ueshima H, Zaky WR, Kadowaki T, Edmundowicz D, Okamura T, Sutton-Tyrrell K, Nakamura Y, Egawa K, Kanda H, Kashiwagi A, Kita Y, Maegawa H, Mitsunami K, Murata K, Nishio Y, Tamaki S, Ueno Y, Kuller LH. Much lower prevalence of coronary calcium detected by electron-beam computed tomography among men aged 40-49 in Japan than in the US, despite a less favorable profile of major risk factors. International Journal of Epidemiology 34:173-179, 2005. 28. Sekikawa A, Curb JD, Ueshima H, El-Saed A, Kadowaki T, Abbott RD, Evans RW, Rodriguez BL, Okamura T, Sutton-Tyrrell K, Nakamura Y, Masaki K, Edmundowicz D, Kashiwagi A, Willcox BJ, Takamiya T, Mitsunami K, Seto TB, Murata K, White RL, Kuller LH; ERA JUMP (Electron-Beam Tomography, Risk Factor Assessment Among Japanese and U.S. Men in the Post-World War II Birth Cohort) Study Group. Marine-derived n-3 fatty acids and atherosclerosis in Japanese, Japanese-American, and white men: a cross-sectional study. Journal of American College of Cardiology 52:417-24, 2008. 29. Briggs RD, Rubenberg ML, O'Neal RM, Thomas WA, Hartroft WS. Myocardial infarction in patients treated with Sippy and other high-milk diets: an autopsy study of 15 hospitals in the USA and Great Britain. Circulation 21: 538-542, 1960. 30. Ganmaa D, Sato A. Mortality from ischemic heart disease in relation to world dietary practices (未発表資料). |