牛乳の生産量はなぜ飛躍的に増大したか ー ウシに穀物と濃厚配合飼料を与えたからである
欧米とて昔から肉や牛乳の消費量が今のように多かったわけではない。畜産品は貴重な換金農産物であった。西洋人の牛乳消費量が増えたのは早くても1930年以降のことである(牛乳の歴史を参照)。
シャープ(Sharpe RM)とスカッケベク(Skakkebaek NE)は、1993年にランセット(Lancet)誌上に発表した外因性内分泌撹乱物質(=環境ホルモン)に関する有名な論文*で、環境ホルモンの一つとして牛乳中の女性ホルモンに言及するとともに、「先進国では乳製品の消費量が多過ぎる。その傾向は1940年代から1950年代に始まった」と述べている。事実、1890年ごろの乳牛1頭からの搾乳量は1日たかだか5リットル程度に過ぎなかったのに、1930年ごろからヨーロッパの牛乳生産量が大幅に増えた。
*Sharpe RM, Skakkebaek NE. Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive tract? Lancet 341: 1392-95, 1993.
現在の遺伝的に改変された乳牛(たとえばホルスタイン)は1日に20〜40kgの牛乳を生産する。しかも、搾乳されている乳牛のほとんどが妊娠している。自分の身体を維持し、胎仔を育てながら、なおかつ20〜40kgのミルクを分泌することは尋常ではできない。まず、ミルクの元となるエネルギー(飼料)を大量に与えなければならない。品種が改変されたとはいえ、牧草だけでこのように大量のミルクを生産することは不可能である(牛乳30kgは2万キロカロリーに相当する)。てっとり早いのはもっと栄養密度の濃い穀物を与えることである。
1908年にハーベル(Haber)が空気中の窒素からアンモニアを合成する方法を開発し、1914年にボッシュ(Bosch)がその大量生産に成功した*。この新技術が農業に安価な窒素肥料を供給をし、穀物を家畜に与えられるほどにその生産量が増大した。さらに、1940年代に始まり、1960年代から1970年代にかけて世界的規模で進行した「緑の革命」(=高収量品種の開発を中心とする農業の技術革新)が一層の余剰農産物を生み出すことになった。この余剰穀物によってミルクの通年生産(自然条件に左右されることなく、人工授精によっていつでも乳牛を妊娠させ、妊娠後半にも搾乳できる)が可能になった**。人間の欲望はこれだけでは終わらない。さらなる奇策を考え出した。
*Frink CR, Waggoner PE, Ausubel JH. Nitrogen fertilizer: retrospect and prospect. Proceedings of National Academy of Science USA 96: 1175-80, 1999.
**Ganmaa D, Wang P-Y, Qin L-Q, Hoshi K, Sato A. Is milk responsible for male reproductive disorders? Medical Hypothesis 57: 510-4, 2001.
人間の欲望はこれだけでは終わらない。さらなる奇策を考えだした。
私たちは、ウシは草原でのんびりと牧草をたべている草食動物であるとぼんやり考えている。しかし、与え方によってはウシは仲間のウシを食う。純粋な植物食であるゴリラが動物園でビフテキが与えられればウシ(ステーキ)を食うように。
現在、日本では毎日3400頭のウシが食用に屠畜されている。大半の日本人はこれらの家畜の筋肉しか食べない(内臓の一部は食用になるが、その量はわずかである)。食用にならない骨と内臓の大部分(脳・神経、胃腸とその内容物など)は焼却される運命にあった。食肉用に屠畜される家畜だけではない。人間と同じように、病気になって死ぬ家畜もいる。このような動物は人間の食用にはならない(ペットの餌にはなる)。死なないまでも病気のために動けなくなり、人間が屠殺場に引きずっていかなくてはならない家畜(英語のdownに倒れた、弱りきったという意味があるので、このような家畜をへたり牛downerという)もいる。これらも埋めるか焼却しなければならない。大仕事である。
しかし、知恵者がいた。骨や内臓を加熱・脱脂したあと乾燥して粉砕する(この工程をレンダリングという)。この粉末(肉骨粉、英語でMeat Bone Meal [MBM]という)を草や穀物と混ぜれば、ウシは仲間を食う。肉骨粉は、ミルクの生産に必須のタンパク質・カルシウムを豊富に含んでいる濃厚動物性タンパク飼料である。見方を変えれば、レンダリングは立派なリサイクルあるいはリユースである。かくて牛乳の生産量はさらに増大した。日本で狂牛病(牛海綿状脳症、BSE)になった36頭(2009年3月現在)のうち、30頭が白黒ぶちの乳牛であったことを奇異に思われた方もいるだろう。18万5000頭に狂牛病が発生したイギリスでは、その85%が乳牛であった。狂牛病は英語でMad Cow Diseaseという。Cowは乳牛である。狂牛病は乳牛の病気であった。現代酪農の牛乳の大量生産が狂牛病の原因であった。
現代の酪農――365日のうち300日搾乳する
現在の酪農では、生後12〜14月の雌ウシを人工授精で妊娠させる(下図)
。
平均280日の妊娠期間(ヒトの妊娠とほぼ同じ)を経て出産すると、母ウシはミルクを分泌するようになる。生まれた子ウシは直ちに母ウシから引き離される。分娩後5日間に分泌される初乳(受動免疫を担う抗体に富む)は子ウシに与えられる。ただし、子ウシが直接、母ウシの乳首から飲むのではなく、酪農家が搾って哺乳容器で子ウシに与える。出産6日後からは人間用に300日搾乳する(通常朝夕2回)。出産2〜3月経つと搾乳中にもかかわらず再び人工授精で妊娠させる。
下に現代の酪農で行われているウシの「人工授精 ー 妊娠 ー 出産」と「搾乳」の関係を図示した。搾乳期間のほとんどが妊娠期間と重なっていることがお解りいただけるだろう。
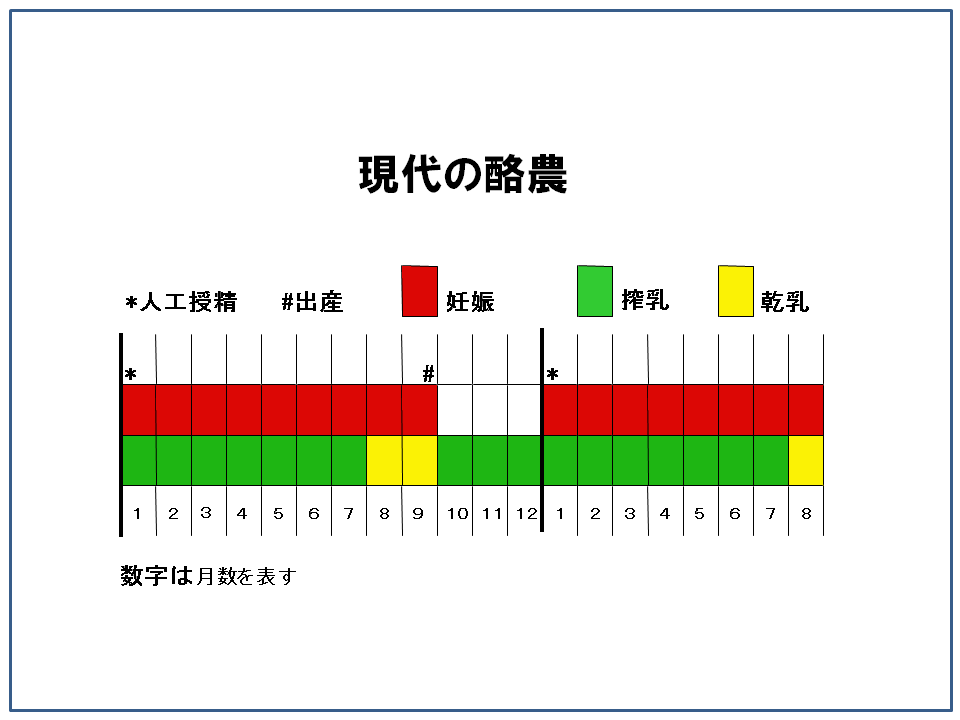
さすがに妊娠最後の60日間は搾乳しない(乾乳という)。毎日2回の搾乳で乳房も痛んでいるし、仔牛が胎内で急速に成長する時期でもあるからだ。人間用ミルクの搾乳期間が300日というのは1年365日から初乳の5日と乾乳の60日を除いた日数である。乳牛は数回の妊娠と出産を繰り返し、泌乳量が落ちると食肉用に屠畜される。かつて、乳牛は4〜6回の出産を経て屠畜されたが、最近の乳牛は2〜3回の出産で廃用牛となる。
現代酪農の乳牛は一生の間に唯の一度も雄ウシと交わることを許されないし、子ウシを産んでも自らの乳首を子に含ませることも許されない。泌乳中にもかかわらず人工授精で妊娠させられる。現代の遺伝的に改変された乳牛は妊娠中にもかかわらず大量のミルクを分泌する。ただひたすら、人間用にミルクを出すのである。このようなことから、乳牛は地球上で最も過酷な労働を強いられる動物であるという人もいる。
肉食の心得――メス動物は食べない
余談であるが牛肉についても一言しておきたい。食用に飼育されている肉用牛(日本で代表的なのは黒毛・赤毛和種などの和牛)は去勢された雄ウシである(生まれた雄の子ウシは種ウシを除いてすべて去勢される運命にある)。雌ウシは繁殖に欠かせないから食用にされるのはずっとのちのことである。未経産の雌ウシの肉が一番うまいという人もいるが、このような肉は高価である。肉用牛だけでなく乳牛が産んだ雄ウシも去勢されて食肉用に飼育される。ただし、肉質の評価は低い。
脂肪に女性ホルモンが含まれているから、雌ウシの肉は食用に不向きである。肉用に屠殺される雌ウシは子を産めなくなった繁殖牛かミルクの分泌量が落ちた乳牛である。いずれも肉質がよくないから安価で取引される。肉用に屠畜される雌ウシなかでは、泌乳量が減ってつぶされる乳牛が圧倒的に多い。市場に出回る全牛肉のおよそ30%はご用済みになった乳牛の肉であるといわれている。さんざんミルクを搾られた末に廃用となった乳牛の肉は旨くない。ひき肉にするかタレに漬けこんで安い焼肉用、煮込んで安い牛丼用に用いるしか使い道がない。安い牛肉の大部分は乳牛のなれの果てである。
最近、廃用になった安価な乳牛を肥育して筋肉に脂肪を入れ「メスに特化した柔らかい霜降り牛肉」などと称して安価で販売されていることがある。「メスの動物は食べない!」はカー二ボア(肉を食べる人)の最低限の心得である。牛肉を買うときは「この肉は雄ウシの肉か雌ウシの肉か」を訊ねてみることだ。
2004年からすべての国産牛肉(小間切れやひき肉などを除く)について、牛の出生から食肉処理場で牛肉に加工され、小売店に並ぶまでの履歴を10ケタの個体識別番号で管理することが義務付けられた。焼き肉屋・牛丼屋でも「オス? メス?」と訊ねよう。判らないなどと答える店が使っている牛肉は輸入ものである。国産牛肉を謳いながら肉の履歴を知らないような店には二度と足を踏み入れないことだ。安いハンバーグがどんな肉を原料にしているかお解りだろう。我が子にひき肉料理を食べさせたいと思ったら、目の前で去勢オス肉のブロックを挽いてもらうことだ。
ウシは妊娠・出産を経てはじめてミルクを分泌する。酪農では、どんな方法でもよいから乳牛を妊娠させて出産させることが必須作業である。ホルスタインの乳牛にホルスタインの精子を人工授精させてもいいし(生まれる子はホルスタイン)、黒毛・赤毛和種の精子の人工授精でもよい(子はホルスタインと和牛の交雑種)。最近では、和牛同士の卵子と精子の受精卵の移植でホルスタインを妊娠・出産させることも行われている(生まれる子は遺伝的には和牛)。ホルスタインは人間でいう代理母となるわけだが、子ウシは和牛として育てられる。
牛乳中の女性ホルモン
現代の酪農は19世紀ごろの酪農と大きく異なっている。根本的な違いは「妊娠しているウシからミルクを搾るようになった」ということである。哺乳類は出産後にミルクを分泌するが、母動物は一般に子がミルクを飲み続けている間は妊娠しない。子の鳴き声、乳首の吸引、乳房の突き上げなどによるプロラクチン・オキシトチンの分泌が排卵を抑制するからであると言われている。
酪農は乳牛に毎年1頭の子ウシを産ませながら乳しぼりを行うことによって成り立つ。そのためには、出産後3か月以内に再び妊娠させなければならない。酪農家は1日に50リットルものミルクを搾る泌乳最盛期のウシに人工授精を試みる。しかし、大量のミルクを分泌しているウシを妊娠させることは難しい。現在の酪農の最大の悩みはウシの不妊である。妊娠しないウシには濃厚な不妊治療が施してでも妊娠させなければならない。
前述のように、最近では受精卵移植も行われることもある(ホルスタインのメスにたとえば黒毛和牛の受精卵を移植すると、ホルスタインが黒毛和牛を産む)。もちろん、この受精卵移植は単にウシを妊娠させるために行われるのではない。和牛の子ウシが高値で取引されるからである。
このように、現代酪農の乳牛はミルクを分泌している最中に妊娠させられる。遺伝的に改変された乳牛は妊娠しながらも大量のミルクを出す。酪農家が濃厚飼料を与え、搾乳器で吸乳し続けるからである。
酪農家は、毎日の牛乳生産量が大きく変わらないようにするため、4種類の乳牛から搾乳する。妊娠していない牛、妊娠前期の牛、妊娠中期の牛、妊娠後期の牛の4種類である。出産直後の5日間と出産前の2ヶ月(乾乳期)を除いて、すべてのウシから人間用に搾乳する。牛乳はタンク内に集められ、牛乳メーカーに出荷されているから、日本の牛乳(もちろん他の先進国においても同様)の4分の3(75%)は妊娠牛から搾乳したものである。
妊娠すると、子宮内に胎仔を保持するために、血中の卵胞ホルモン(エストロジェン)と黄体ホルモン(プロジェステロン)の濃度が高くなる。ミルクは血液からつくられるから、妊娠中の乳牛から搾ったミルクにはこれら女性ホルモンが多量に含まれている。
エストロゲンとは卵胞ホルモンあるいは発情ホルモンと呼ばれる女性ホルモンの総称である。思春期の性発達を促すとともに性周期(月経)の発現に重要な役割を果たしている。妊娠すると、主として胎盤から分泌され、子宮の発育を促す。妊娠期間を3期に分けると、分泌量は前期<中期<後期の順に多くなる。一方、プロゲステロンとは黄体ホルモンと呼ばれる女性ホルモンを指す。卵巣の黄体から分泌され、子宮内膜を受精卵が着床可能な状態にする。妊娠すると、主として胎盤から分泌され、妊娠を維持するように働く。
ヒープ(Heap RB)とハモン(Hamon M)*によれば、妊娠していないウシから搾乳した乳汁の乳清(ホエイ)には約30pg/mLの硫酸エストロン(estrone sulfatee:エストロンの硫酸抱合体)が存在する。ウシが妊娠するとその濃度が高くなり、妊娠41〜60日には151pg/mLとなり、妊娠220〜240日には1000pg/mLに達するという。この硫酸エストロンは、口から入ってエストロジェン作用を示す女性ホルモンである。事実、妊娠馬の尿から抽出・精製される硫酸エストロンがプレマリンという名の天然経口ホルモンとして婦人科医療(ホルモン補充療法)に用いられている。
*Heap RB, Hamon M. Oestrone sulphate in milk as an indicator of a viable conceptus in cows. Br Veter J 135: 355-363, 1979.
牛乳中の女性ホルモンは熱に強いので、加熱滅菌によって分解されない。したがって、市販の牛乳は女性ホルモン(数百pg/mLの卵胞ホルモンとその数十倍の黄体ホルモン)を含んでいる。言い換えれば、牛乳は「妊娠したウシの白い血液」である。現在のアイスクリーム・チーズ・バター・ヨーグルトなどの乳製品はみな、妊娠牛が分泌する、女性ホルモン入りの「白い血液」から作られている。
ミルクは健康的な飲み物で、ビタミン・ミネラルなどの栄養素を豊富に含む純白の液体である考えている方もおいでだろう。しかし、この「健康的な飲み物」は巧みにつくり上げられた幻想に過ぎない。哺乳動物のミルクは、赤ん坊の成長と発達を促すために、たくさんのホルモンやホルモン様物質を含んでいる生化学的液体(ホルモンカクテル)である。ミルクは、単に養分を与えるだけでなく、細胞の分裂と増殖を刺激して赤ん坊の急速な成長を促す。ミルクに含まれている最も強力な成長因子は、インスリン様成長因子1(IGF-1)と呼ばれるホルモン様物質である。当然のことながら、離乳期を過ぎた哺乳動物の子は母親のミルクを飲まない。哺乳類に離乳という現象が存在するのは、子どもがいつまでもミルクを飲みつづけていると母親が次の子を宿すことができないからであることは「日本人と牛乳」で述べた。人間は、離乳後にもミルクを飲み続ける唯一の哺乳動物である。
ミルクは、それがヒトのもの(母乳)であれウシのもの(牛乳)であれ、親が赤ん坊に与えるべき数百種類もの物質を含んでいる白い液体であることに心してほしい。要するにミルクは、同種の動物の子どもの成長・発育に適うように精密に造られた非常に複雑な生化学的液体なのである。牛乳が悪い飲み物というわけではない。それはすばらしい飲み物である、ただし子牛にとって。ここに昨今の牛乳問題の本質がある。
牛乳は急速に成長する子ウシ(体重が1日に1kgも増える!)にとって完璧な飲み物であるが、人間の子ども(体重が1kg増えるのに1ヵ月かかる)にとってもよいものかどうかわからない。牛乳が離乳期を過ぎた人間にとってよいものではないというのは、それがウシという異種動物のミルクであるからではない。加熱しても加工しても消えることのない成長促進作用を示す物質だからである。
牛乳を通して子どもの体内に入る女性ホルモンは許容摂取量を超えている
現代の牛乳が抱える最も大きな問題は牛乳中の成長因子(IGF-1)と女性ホルモンである。牛乳に含まれている女性ホルモン ――エストロジェン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)―― は人間のものと同一である。本物のホルモンだから、牛乳のホルモン作用は環境ホルモン(外因性内分泌撹乱物質)などと呼ばれる化学物質のホルモン作用に比べて桁違いに大きい。とくに、前思春期の子どもは性ホルモンの影響を受け易い*。それにもかかわらず、酪農業界と関係の深い学者たちは「牛乳のホルモンは、女性の体内を流れているホルモンの量に比べれば微々たるものである」という。この人たちは、現代の牛乳が「妊娠したウシの白い血液」であるということを忘れている。 *Aksglaede L, Juul A, Leffers H, Skakkebaek NE, Andersson A-M. The sensitivity of the child to sex steroid: possible impact of exogenous estrogens. Human Reproduction Update 12: 341-9, 2006.
この人たちの反論根拠は、アメリカ食品医薬品局(FDA)が定めた性ホルモンの許容摂取量(安全摂取量)(http://www.fda.gov)にある。彼らは、牛乳を通して人間の体内に入る女性ホルモン量はFDAの許容摂取量に比べると少ないと主張する。だから、牛乳は安全であると言うのである。本当にそうなのか。
体内の女性ホルモン濃度が最も低いのは前思春期の男の子(小学生:6〜11歳)である。FDAは、前思春期の男の子の体内で1日につくられる女性ホルモン量(体内産生量)の1%を食品からの女性ホルモンの許容摂取量と定めている。このこと自体に問題はない。ところが、FDAは実際の安全量をはるかに超える数値を許容摂取量と決めているのである。なぜこんなことになってしまったのか。エストロジェンの一つであるエストラジオールを例にとって説明しよう。
FDAは、許容摂取量の設定にあたって、前思春期男子のエストラジオールの体内産生量として6・5マイクログラム(マイクログラム=100万分の1グラム)という数値を採用した。この数値は「食品添加物に関するFAO/WHOの合同食品添加物専門家会議(JECFA)が提案した数値*である。したがって、6・5マイクログラムの1%である65ナノグラム(ナノグラム=10億分の1グラム)がエストラジオールの許容摂取量となる。
*The Joint FAO/WHO Expert Committee on food additives (1988) Evaluation of certain veterinary drug residue in food. World Health Organization, Geneva. WHO Technical Report Series 763.
しかし、FDAが許容摂取量の算出根拠に用いた前思春期の男の子のエストロジェンの体内生産量は極めて疑わしい数値で、その許容摂取量には多くの疑問が寄せられている*-***。
*Andersson AM, Skakkebaek NE. Exposure to exogenous estrogens in food: possible impact on human development and health. European Journal of Endocrinology 140: 477-85, 1999.
**Dexenberger A, Ibarreta D, Meyer HH. Possible health impact of animal oestrogens in food. Human Reproduction Update 7: 340-55, 2001.
***Partsch CJ, Sikppel WG. Pathogenesis and epidemiology of precocious puberty. Effects of exogenous oestrogens. Human Reproduction Update 7: 292-302, 2001.
あるホルモンの体内産生量は、そのホルモンの血漿濃度と代謝クリアランス(MCR:ホルモンが血液中から代謝によって除去される速度で、単位時間に除去されるホルモンを含む血漿量で表される)から次式で求められる。
体内産生量(マイクログラム/日)=血漿濃度(マイクログラム/ミリリットル)
x MCR (ミリリットル/日)
したがって、前思春期の男の子のエストラジオールの体内産生量の推定値は、このホルモンの男の子の血漿濃度の測定値に大きく左右される(血漿濃度が高ければ体内産生量の計算値が大きくなる)。JECFAは、前思春期の男の子のエストラジオール産生量の計算に、1)古い方法で測定した著しく高い男の子の血漿エストラジオール濃度を用い、2)前思春期の男の子に比べて非常に大きい、成人女性の代謝クリアランスを採用した。したがって、JECFAが計算した前思春期の男の子のエストラジオールの体内産生量は実際の数値に比べて100〜200倍も高くなっている*。つまり、FDAは、実際の数値より100〜200倍も高い数値を許容摂取量と定めているのである。
*Andersson AM, Skakkebaek NE. Exposure to exogenous estrogens in food: possible impact on human development and health. European Journal of Endocrinology 140: 477-85, 1999.
クライン(Klein KO)の新しい測定値* **に基づいて計算しなおすと、前思春期男子のエストラジオールの体内産生量は0・04〜0・1マイクログラム(=40〜100ナノグラム)になる***。体内生産量を0・04マイクログラムとして計算すると、許容摂取量は0・4ナノグラム(=0・04マイクログラムの1%)となる。仮に体内産生量が0・1マイクログラムであるとしても許容摂取量は1ナノグラム(=0・1マイクログラムの1%)となり、FDAの許容摂取量の65分の1である。
*Klein KO, Baron J, Colli MJ, McDonnell DP, Cutler GB Jr. Estrogen levels in childhood determined by an ultrasensitive recombinant cell assay. J Clin Invest 94:2475-80, 1994.
**Janfaza M, Sherman TI, Larmore KA, Brown-Dawson J, Klein KO. Estradiol levels and secretory dynamics in normal girls and boys as determined by an ultrasensitive bioassay: a 10 year experience. J Pediatr Endocrinol Metab 19: 901-909, 2006.
***Andersson AM, Skakkebaek NE. Exposure to exogenous estrogens in food: possible impact on human development and health. European Journal of Endocrinology 140: 477-85, 1999.
前思春期の子どものエストラジオール産生量に関して完全に意見の一致がみられているわけではないが、最近の研究はすべて前思春期のホルモンレベルがかつて信じられていたよりもずっと低いことを明らかにしている。さらに将来、成人女性の代謝クリアランス(MCR)ではなく子どものMCRが計算に用いられるようになったら、実際の許容摂取量はさらに低くなるであろう。
因みに現在の日本の前思春期〜思春期の子ども(6〜14歳)は平均して1日300グラムの乳・乳製品を摂っている。私たちが測定した市販牛乳の硫酸エストロン濃度は0・378ナノグラム/ミリリットルであった*。この数値を採用すると1日当りのエストロン摂取量は110ナノグラムに達する。さらに、「日本人と牛乳」で述べたように、この300グラムという摂取量は国民健康・栄養調査の数値で、実際の乳・乳製品の摂取量はこの1・5倍の500グラムにのぼると推定される。すなわち、エストロンだけで計算しても、現在の日本の子どもたちは体内産生量と同等量あるいはそれ以上の女性ホルモンを乳・乳製品から毎日摂りつづけているのである。
*Qin LQ, Xu JY, Wang PW, Ganmaa D, Li J, Wang J, Kaneko T, Hoshi K, Shirai T, Sato A. Low-fat milk promotes the development of 7,12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA)-induced mammary tumors in rats. International Journal of Cancer 110: 491-496, 2004.>
牛乳中の女性ホルモンが小児に吸収されることを見事に証明したMaruyamaたちの研究がある*。牛乳を飲んだ後に尿中に排泄されるエストロジェンが増えれば、牛乳のエストロジェンが吸収され、身体をめぐりめぐって腎臓から尿中に排泄されたことの証明になる。Maruyamaたちは7歳3ヶ月から9歳9ヶ月の前思春期の子ども7人(男子3人、女子4人)に単位体表面積当たり600ml(飲用量490〜640ml)の市販牛乳を10分以内に飲ませて、飲用前後に尿中に排泄されるエストロン・エストラジオール・エストリオールを測定した。1名の女子は490mlを飲むべきところ180mlしか飲めなかった。この1名を除いた6名についての牛乳飲用前後の尿中エストロジェン濃度が測定されている(下図)。

尿中に排泄されるエストロン・エストラジオール・エストリオールは牛乳飲用の1持間後から増加しはじめ4時間以内にピークに達した。その増加は統計学的に有意であった。牛乳には多量の脂肪が含まれているために全乳のエストロジェン濃度を測定することは難しい。しかし、尿中のエストロジェン濃度の測定は容易である。本人と保護者が承諾し、倫理委員会の許可が得られたら、乳・乳製品の摂取による尿中エストロジェンの増加を追試・確認して欲しい。

「牛乳製造工場で加熱処理をしているから、牛乳中の性ホルモンは活力を失っている」という驚くべき意見を述べる酪農団体の御用学者もいる。しかし、ステロイド骨格の性ホルモンは現行の125〜130度の高熱滅菌で壊れないことはすでに実証済みである。事実、以下に述べるように、日本で市販されている高温滅菌の牛乳はホルモン作用を示す。牛乳の女性ホルモンが高温によって破壊されないことを示す何よりの証拠である。
市販の牛乳には女性ホルモン作用がある
1960〜70年代に乳児用調整粉ミルクで子どもを育てることが流行した。この粉ミルクの原料の70%は牛乳であった。今となっては測ることはできないが、この調整粉乳にも相当量の女性ホルモンが含まれていたに違いない。第二次ベビーブームと呼ばれた1970年代前半に生まれた世代(団塊ジュニア)の相当数は乳児用粉ミルクで育てられたことだろう。そしてその後も保育園・幼稚園・小学校・中学校で女性ホルモン入りの牛乳をほぼ強制的に飲まされた。この子たち(とくに男の子)はまともに性発達を遂げただろうか。960万人もいる団塊ジュニアは2010(平成22)年には35〜40歳になった。この世代が第三次ベビーブームをもたらすことは絶望的である。
それでは、市販の牛乳にホルモン作用があることを確認した研究*を紹介しよう。女性ホルモン作用を実験的に確認する方法に子宮肥大試験という方法がある。卵巣を摘出した成熟雌ラット(子宮が萎縮する)あるいは未成熟の雌ラット(子宮が未発達)に試験物を注射あるいは飲ませて子宮が大きくなるかどうか確認する試験法である。この方法は、まるごとの動物を使う試験法なので培養細胞などを用いる試験法に比べて信頼性が高い。
*Ganmaa D, Tezuka H, Enkhmaa D, Hoshi, Sato A. Commercial cows’ milk has uterotrophic activity on the uteri of young ovariectomized rats and immature rats. International Journal of Cancer 2006, 118: 2363-5.
この方法で、妊娠しているウシから搾られた市販の高温で滅菌された牛乳が飲用で女性ホルモン作用を示すことが確認された。すなわち、牛乳を与えると、卵巣摘出によって萎縮した成熟ラットの子宮が大きくなり、未成熟ラットの子宮がより速やかに成長した。牛乳の影響は成熟ラットより未成熟ラットに強く現れた。すなわち、牛乳ホルモンの影響はおとなよりも、性的に未熟な子どもに強く現れるのである。この研究結果はロイターヘルス(Reuters Health)に取りあげられたが、日本のマスコミはこれを無視した。
なお最近、妊娠しているウシから搾られた市販牛乳の子宮肥大作用(女性ホルモン作用)はモンゴルの、妊娠していないウシから搾られた牛乳の作用より有意に大きいことが報告されている*。
*Zhou H, Qin LQ, Ma DF, Wang Y, Wang PY. Uterotrophic effects of cow milk in immature ovariectomized Sprague-Dawley rats. Environ Health Prev Med 2010, 15: 162-168.
世の中のお母さん方は、自分の子どもが飲んだり食べたりしている牛乳や乳製品がよもや妊娠しているウシから搾られた牛乳を原料にしているなどとは夢にも思わないだろう。母親は、自分の妊娠・出産・授乳の経験から、子どもが母乳を飲んでいる間は妊娠しないことを知っているからである。ところが現実には、遺伝的に改変された乳牛は泌乳中に妊娠し、妊娠中にもかかわらず大量のミルクを分泌するのである。
妊娠しているウシの体液(ミルク)を子どもに飲ませる母親がいるだろうか。前思春期の子どもに毎日、女性ホルモン入り牛乳を大量に飲ませるということは、極言すれば、前思春期の子どもに低用量避妊ピルを毎日飲ませているようなものである。年端もいかぬ子どもに避妊ピルを飲ませる母親が果たしてこの世にいるだろうか。
くり返すが、牛乳中のホルモンは本物のホルモンであるから(ウシの女性ホルモンは人間のものと同じ)、そのホルモン作用は外因性内分泌撹乱物質(環境ホルモン)などとは比べようがないほど強いのである。
覚えておられる方も多いだろうが、1990年代に、環境ホルモンをめぐって世界中が大騒ぎしたことがあった(シーア・コルボーン、ダイアン・ダマノスキ、ジョン・ピーターソン著、長尾力訳『奪われし未来』翔泳社、1997年9月;デボラ・キャドバリー著、井口泰泉監訳・古草秀子訳『メス化する自然−環境ホルモン汚染の恐怖』集英社、1998年2月)。日本でも、子どもを育てるのに母乳(微量のPCB・ダイオキシンが含まれている)がいいか、人工ミルク(哺乳瓶から環境ホルモンのビスフェノールAが溶出する)がいいかなどという不毛かつ罪作りな議論がメデイアを賑わせた。