なぜ、乳がんが増えているのかー理由は乳がん検診(マンモグラフィ)
前章の「牛乳と乳がん」で掲げた乳がんの年齢別罹患率の図を再掲する。2010(平成22)年の乳がん罹患率が2000(平成12)年までの罹患率に比べて飛び抜けて高くなったことが判る。
2010(平成22)年の新規乳がん患者は7万6041人であった。1975(昭和50)年の新規乳がん患者数が1万1123人であったから、乳がん患者は1975〜2010年の35年間に約6.8倍に増えたことになる。さらに注目すべきことに、2010年の新規患者数は、2000年の新規患者3万7389人に比べて、実に3万8652人も多くなった(10年で2倍)。
この乳がん増加は尋常ではない。こんなに乳がん患者が増えたのは、「早期発見・早期治療」の掛け声によって、乳がん検診(とくにマンモグラフィ)が患者の発掘に努めたからである。検診が盛んに行われると乳がんが増えることを知っておくべきだ。検診はがんを見つけているのであって、がんの発生を防いでいるわけではない。乳がんの検診率がいくら上がっても、乳がんになる女性が減ることはあり得ない。乳がんの発生要因(食生活の欧米化=乳食文化の浸透)を野放しにしているからである。
ただし、増え続けてきた日本人の乳・乳製品の消費量が1995年ごろから停滞するようになった(第一章 日本人と牛乳)。この消費量の変化は30年ほど経ってから乳がんの発生に影響をおよぼす。日本の乳がんの発生率と死亡率はいずれ、乳がん検診ではなく乳製品消費量の停滞によっていずれそのうちに高止まりするだろう。
がんとはどんな病気か
日本のがん対策の中核は検診で、厚生労働省も地方も受診率を上げることに躍起となっている。受診者は「早期に発見すればがんは治る」と信じて検診を受ける。ところが、検診で見つかるがんには進行の遅いがん多く、検診は命にかかわるような進行がんを防ぐことにはあまり役立たない。こんなことを聞くと眼を剥く方もおられるだろうが、後述の「がんの自然史」をお読みいただければ理解していただけるだろう。
がんとはどんな病気なのか。吉田富三博士(1903〜73年、がん研究者にして思想家、1959年文化勲章)は「初めは音もなく訪れ、一旦それと診断された暁には、死から免れ得ない病。家庭的にも、社会的にも、中核をなす人々を襲う業病。それが癌である。宿主細胞より生まれ、宿主を殺すまで増え続け、宿主の死とともに自らの命をも絶つ不思議な生物系。それが癌である」と述べた。周辺の組織に侵入する(浸潤)、遠く離れた臓器・組織に転移する、宿主の命を奪うまで増え続ける、という3つの性質を兼ね備えたものが、吉田博士の定義するがんである。
かつてはがんと診断されるとほどなくして死が訪れた。吉田博士の定義にしたがえば、手術で腫瘤を取り除いたら治ったなどというものはがんではない。医学界におけるこのがんの定義が普及して、「がん=不治の病(やまい)」が、医師のみならず一般人の確固たる通念となった。
ところが、精密な診断機器を用いることによって、臓器・組織の小さな異常が見つけられるようになると、「がんは早期に発見して治療すれば治る」という「早期発見」仮説が広まるようになった。かくして1960年代に、健康人に検診を行ってがんの早期発見・早期治療を目指す時代の幕が上がったのである。
がんが小さいうちに見つけられるようになってから、がんという病態がすべて同じ経過をたどるわけではないということもわかるようになった。病理医ががんと名付ける異相の顔つきの細胞集団が、ほんの数か月で命を奪うほどに成長するものがある一方で、ほとんど分裂増殖せず長年にわたってそのままの状態にとどまるものもあるということがわかってきたのである。
がんの自然史
検診を受けないで進行がんになった人は「何でこんなになるまで放っておいたのか」と医師に責められ、「定期的に検診を受けないからこんなことになったのだ」と周りに責められ、「真面目に検診を受けなかった自分が悪い」と自分を責める。そんなことはない。この人たちに「検診を受けなかったから進行がんになったわけではありません」ということを伝えるために、藤田晢也京都府立医科大学名誉教授の「癌の自然史*」に沿って以下の文章を書く。
*藤田晢也: 癌の自然史. 現代病理学大系, 9巻C, p.225-243, 中山書店, 東京, 1984.
がんは一個のがん細胞の分裂から始まる。細胞数は1回の分裂で2個、2回分裂すると4個、3回で8個、さらに16、32、64個と増えていく。つまり、n回の分裂によってがん細胞の数は2のn乗になる。10回の分裂でがん細胞数は1000個(2の10乗)となり、20回の分裂で100万個(2の20乗)、30回で10億個(2の30乗)となる。
分裂によってがん細胞の数とがんの大きさ(体積と重量)は2倍(ダブル)になる。がんの大きさが2倍になるのにかかる時間を倍加時間(doubling time、ダブリングタイム)という。ダブリングタイムをDで表すと、10回の分裂に10D、n回の分裂にはnDの時間がかかることになる。
がん細胞の数(体積)をDとの関係で示すと下図のようになる。この図は最初1個の細胞が一定のダブリングタイムDで生長しつづける場合を示したものである。肉眼でがんの生長を観察するとa図のような経過(指数曲線)をたどり、半対数グラフに描くとb図のような直線的生長になる。
大きさ10ミクロンのがん細胞が分裂してがんの塊が1ミリの大きさまで生長するのにかかる時間は20Dである。この過程を別の尺度から眺めると、出発点となった10ミクロンのがん細胞に比べて、直径は100倍、体積は100万倍という塊(かたまり)に生長している。がん細胞が100万個も集まって塊をつくっているのに、この段階では患者も医師も病変の存在に全く気づかない。
10ミクロンから1ミリの塊に生長するのにかかる時間は極めて短いように思えるが、それは間違っている。Dを仮に1年とすると10ミクロンから1ミリに生長するまでに20年もかかっているのである。
30回の分裂(30D)で、がん細胞は10億個(10の30乗)に増える。がんは直径10ミリ(1センチ)程度に生長し、やっと「早期がん」として発見されるようになる。このあとさらに10回も分裂すれば直径10センチ、重さ1キロの巨大な腫瘤(細胞数1兆個)に生長する(図中に黒の十字で示した時点)。もはや致命的なサイズである。これ以上の腫瘍の生長に通常ヒトは耐えられない。もう10Dたつと、腫瘍塊は直径1メートル、重さ1トンになってしまう。つまり、がんという「宿主の死とともに自らの命を絶つ不思議な生物系」の命数は40D*である。
*ダブリングタイム(D)はそれぞれのがんによって違うが、「癌の自然史」の著者藤田晢也名誉教授はご自身の観察をもとに推定した胃がんの全経過(40D)を16〜33年、平均25年という数値を提示しておられる。
発見されるまでのがんの生長はしごくゆるやかである。30Dという長い年月(Dを1年とすると30年)をかけて初めて発見されるような大きさになる(a図)。このあたりからがんの大きさがめだって増してくる。そのため、がんというものは発見される時点(図の↑)の直前に発生し、その後爆発的に生長するかのように誤解されてきた。がんの自然史を無視したために生じたこの誤解が、以下に述べる「がんもどき論争」の出発点となっている。
かつて吉田富三博士はがんについて「初めは音もなく訪れ、一旦それと診断された暁には、死から免れ得ない病」と述べた。吉田が活躍していた時代、がんは発生から40D近く経って発見された。30Dでは症状も出ないからそもそも医師にかかることはなかったし、たとえ自覚症状が現れてもがんの診断は不可能であった。この時代には、がんはまさしく「宿主細胞より生まれ、宿主を殺すまで増え続け、宿主の死とともに自らの命をも絶つ不思議な生物系」であった。治療が奏効するようなものはがんではなかった。完治したなどというと「がんでないものをがんと誤診したからだ」と云われたものであった。
ウェルチの分類と近藤誠氏のがんもどき
1万人のがん患者の病状の経過は1万通りあるが、ウェルチ(Welch)はがんの進行過程を4つに大別して説明している*(図)。
*Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst 2010, 102:605-613.
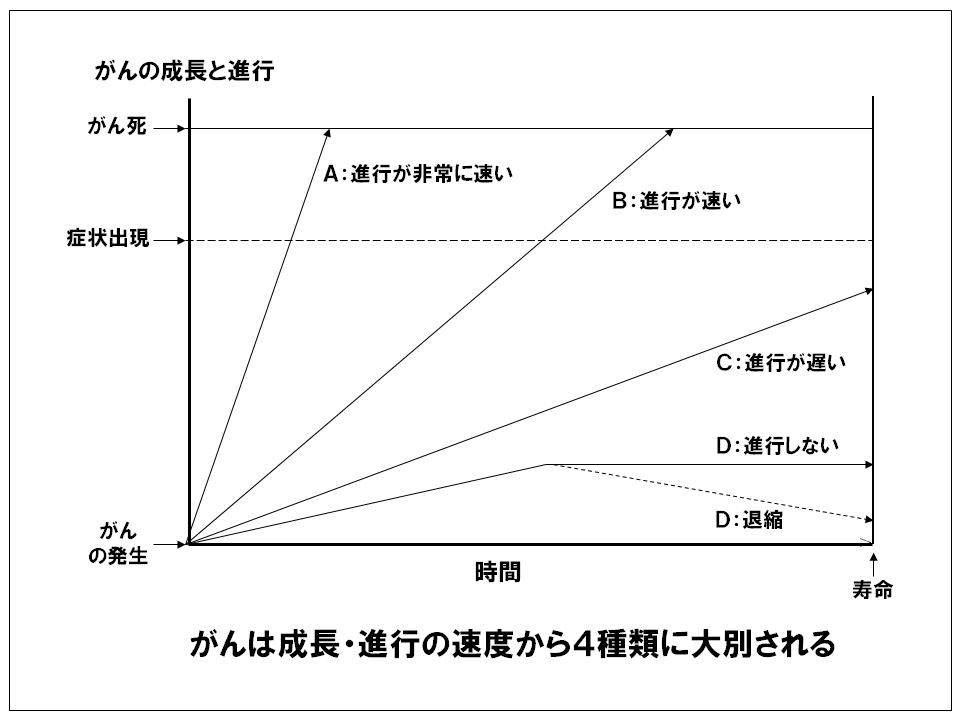
Aは生長が極めて速くたちまちのうちに宿主(ひと)の命を奪ってしまうがん、Bは生長はそれほど速くないがやがて症状が現れいずれ命を奪うことになるがん、Cは生長が遅く命を奪うほどには進行しない「がん」、Dはほとんど生長せずときには退縮してしまうこともある「がん」、の4種類である(この図は模式図であって、当然のことながら、がんの生長・進行がこの図のように直線的な経過を示すわけではない)。後で述べるように、がん検診で見つかる「がん」にはCとDが多いこともわかってきた。
「先生、なんとか助けてください」と家族の懇願を受けてAが治療を受けると患者が苦しむ。Aには緩和ケアが主体となる。Bでは、他の病気や事故で命を落とさないかぎりそのがんで最期を迎えることになるが、ほころびを繕うように処置していくと、死が先送り(延命)される可能性がある。この場合、生命の総時間と苦痛との調和が課題となる。CとDの場合には、不都合が生じた時点でそれなりの処置を受けることによって天寿を全うする。
慶応大学の近藤誠氏は、1996年の『患者よ、がんと闘うな』(文藝春秋)や2010年の『あなたの癌は、がんもどき』(梧桐書院)などで一貫して「がんもどき」仮説を唱え、現今の医学界の主流である「早期発見」仮説と激しく対立してきた。
近藤氏は、がんには「本物のがん」と「がんもどき」の二つがあると主張する。「本物のがん」は、ウェルチのAとBで、吉田富三博士の「一旦それと診断された暁には、死から免れ得ない病。宿主細胞より生まれ、宿主を殺すまで増え続け、宿主の死とともに自らの命をも絶つ不思議な生物系」である。一方、「がんもどき」は「本物のがんに似て非なるもの=がんのようなもの」に対する近藤氏の造語*で、ウェルチのCとDである。
*「がんもどき」は日本の医学界では禁句である。海外では「がん; Cancer」は恐怖心を与えるから、「進行しない上皮性起源の異型細胞の集団」を「Cancer」に替えて「IDLE」(Indolent Lesion of Epithelial Origin)と呼ぼうという提案**がなされている。日本語では「のんびり」「ゆっくり」「おっとり」といったところか。最近、読者から、「IDLE」の日本語訓みで「アイドル」と呼んだらどうかという提案をいただいた。それも面白い。
** Esserman LJ, Thompson IM, Reid B, et al. Addressing overdiagnosis and overtreatment in cancer: a prescription for change. Lancet Oncol. 2014 May;15(6):e234-42. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70598-9.
近藤誠氏の「がん検診無用論」
近藤氏のがんもどき理論は、数十億から数百億個のがん細胞からなるがんの塊はもともと1つの細胞が分裂・増殖したものであるというがん幹細胞仮説に基づいている。このがん幹細胞に転移能力があれば転移するし(本物のがん)、なければ転移しない(がんもどき)というのが近藤理論である。がん幹細胞のすべてを「ほんもの」と「もどき」に二分できるのかどうかわからないが、死にいたるものは「ほんもの」(ウェルチのAとB)、治るようながんは「もどき」(CとD)とする区分けは単純でわかりやすい。吉田富三博士の時代(1950年代)にはがんとは死にいたるもので治るようなものは誤診であると考えられていたことは先に述べた。
乳がんを例にとると、「早期がん」という用語は一般に大きさが2センチ以下の腫瘍に対して使われる。この大きさに生長するには30D以上の時間が経過している。命数(40D)の3/4が経過した生物系を「早期がん」と呼んでいるのである。寿命80年の人間なら60歳に相当する。がんの30Dは少年期・青年期というよりは老年期だろう。
発見された時点ですでに30Dもの時間が経過している。「転移能力のあるがん(=本物のがん)なら、がんが‘早期’に発見された時点ですでに転移している。30D経っても転移しなかったがんは、もともと転移する能力がないので、その後も転移しない」とする近藤氏のがんもどき理論は「がんの自然史」からみて不自然ではない。もちろん、30D後に新たに転移能力を獲得する可能性はゼロではないだろうが。
近藤氏は「本物のがんは検診で発見されるころにはすでに転移しているから早期発見は無意味である。本物のがんが早期に発見されると苦しい治療を長期間にわたって受けたあげくに結局死亡する。本物のがんは早期ではなく末期発見が望ましい」と主張する。一方、「がんもどきは転移しないから放置しても命にかかわることはない」と近藤氏は断言する。「人間のがんは本物のがんかがんもどきのいずれかである。どちらにしてもがん検診は有害無益」。これが近藤氏の唱える「がん検診無用論」である。
近藤仮説は、論理の組み立てが巧みで、一部の読者から圧倒的な支持を得ているようだ(本がよく売れている)。ただ、「どんな病気だって早く見つけて治療すればよくなるのではないか」と考えている医師や一般の方々の理解を得ることはなかなか難しい。また、近藤氏は日本のがん診療の欠陥を数字で厳しく突いているから、なまなかのがんの専門家ではまともに近藤理論に太刀打ちできない。ほとんどの専門家は、「死ねば本物で、死ななければもどきという単なる結果論に過ぎない」と一刀両断するか、「もどきが本物に変異する確率は正常細胞からがん細胞ができる確率より大きい」と反論する。なかには「私は30年もがん検診に一身をなげうってきた。この努力がまったく無駄であったというのか!」と怒り狂う人もいれば、「‘がんもどき’なんてものはない! あるのはおでんの中だけだ」などと過激に反応する人もいる。
がんの転移
ほとんどのがんで転移のあるなしが生死をわける。早期発見が叫ばれるのは、転移する前に発見して治療すれば、がんは治るのではないかという祈りにも似た思いが広く行き渡っているからである。早期発見仮説は「がんは小さいうちは転移しない」ことを前提としている。
「がんの自然史」でも述べたが、がんは大きくならないと転移しないというのは誤解である。このような誤解が起こるのは、私たちが自分の知識・経験から、転居・自活などという独立行動はある程度成長してから行われるものだと思っているからだろう。たしかに、幼児が独りでさまよい歩いて他人の家に住みつくなどということは考えられない。だから、がん細胞の転移もがんが大きくなってから起こるのだと信じてしまうのである。
しかし、「宿主細胞より生まれ、宿主を殺すまで増え続け、宿主の死とともに自らの命をも絶つ不思議な生物系」のがん細胞は誕生した瞬間から自律性をもって行動する、生まれながらにして我と我が身に巣食う「鬼子」である。「鬼子」は自分で決めた規律にしたがって気ままに遊走して自分に適った臓器にもぐりこんでそこに住みつく。肉眼では見えない微視的転移である。肺に住みついたがん細胞は乳がんの性質を保ちながらも、肺で増殖しやすいように周りに合わせて姿形を変える。したがって、原発巣(乳がん)が見つかる前に肺がん(転移乳がん)が発見されることもある。
乳がんを「早期」に発見して治療を受けたのに、その数年後に肺に転移が見つかったという話を聞く。このようなケースでは、初発巣(乳房)の発生から間もなくして転移が起こったと考えるのが妥当である。転移巣(肺)も、転移してから20〜30D経って、発見されるほどの大きさにまで生長する。このようながんが「早期がん」と言われるのは、転移巣がまだ小さくて初発巣の治療時点では発見されなかったからである。これは本物のがん(ウェルチのB)にときどきあることで、必ずしも稀有な出来事ではない。
「顕微鏡を考える道具とした思想家」と言われる吉田富三は50年以上も前にこのようながん細胞の特徴を巨細に観察していた。吉田は「癌(がん)は身の内」という言葉をよく口にしていたらしい(吉田直哉『私伝・吉田富三 癌細胞はこう語った』文藝春秋、1002年11月)。単なる不良なら摘み出すこともできるが、本物の身の内のがん(鬼子)を退治する手立ては我と我が身を焼き尽くすほかない。
問題はがんと診断される病変のうち本物のがんはどれくらいあるのかということである。日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死ぬと言われている。これが本当なら、日本のがんの60〜70%が本物のがん(ウェルチのAとB)で、残りの30〜40%ががんもどき(CとD)ということになる。大雑把なものだが、この数字は真実からそんなに遠いものではあるまい。近ごろ「がんが治るようになった」と言われるのはがんもどきが治療を受けているからではないかという推論も成り立つ。
検診で見つかるのは進行の遅い「がん」
定期的に乳がん検診を受けていたひとが半年前のマンモグラフィで異常がないと言われたのに胸のしこりに気づいて病院に行ったら進行性の乳がんと診断されることがある。別に驚くことではない。これが乳がん検診の常態である。検診の合間に見つかるがんは中間期がん(interval cancer)と呼ばれ、検診で発見されるがんより悪性度が高いことが昔から知られている*2。上述のウェルチのAあるいはBのような進行の速い乳がんが先の検診では異常なしであったのに次の検診を受ける前に自分で気づくほどに大きくなって発見されたのである。
*2Ikeda DM, Andersson I, Wattsgard C, Janzon L, Linell F. Interval carcinomas in the Malmo¨ Mammographic Screening Trial: radiographic appearance and prognostic considerations. AJR Am J Roentgenol. 1992, 159:287-94.
進行の速いがんは短い間に大きくなりやがて症状が現れる。だから、6か月前の検診では「異常なし」と判定されたのに、胸のしこりに気づいて乳がんと診断されることがある(中間期がん)。これに対して、ウェルチのCとDのような「がん」は気づかれることなく長い間体内に存在する。このような進行の遅い「がん」は検診を繰り返すことによって発見される機会が増える。つまり、検診で発見されるがんはゆっくり進行するものが多い。
別の言い方をすれば、乳がん検診は命に関わることの少ないがんの発見に努めていることになる。この現象は「進行速度によるバイアス」(length bias)と呼ばれている。レングス(length)はがんができてから発見されるまでの時間の長短である(滞在時間)。わかりやすく言うと、時速60キロで走っている自動車の運転手を言い当てることは難しいが、10キロで走っている車なら誰が運転しているのかわかるということである。
がん検診の有効性を「生存率」で評価してはならない
検診で発見された乳がんは生存率(乳がんの治療を受けた人が5年あるいは10年後に生存している割合)の高いことが検診の利益として強調される。しかし、検診乳がんの生存率が高いのは当然であって、生存率で検診の有益性を評価してはならない(国立がん研究センター がん予防・検診研究センター検診研究センター 検診評価研究室 なぜ「生存率」ではだめなのか)。
検診発見のがんは症状が現れて見つかるがんよりX年早く診断されるから、がんが見つかってからX年長く生きるのである。これを「先行発見によるバイアス」(lead time bias)という(図)。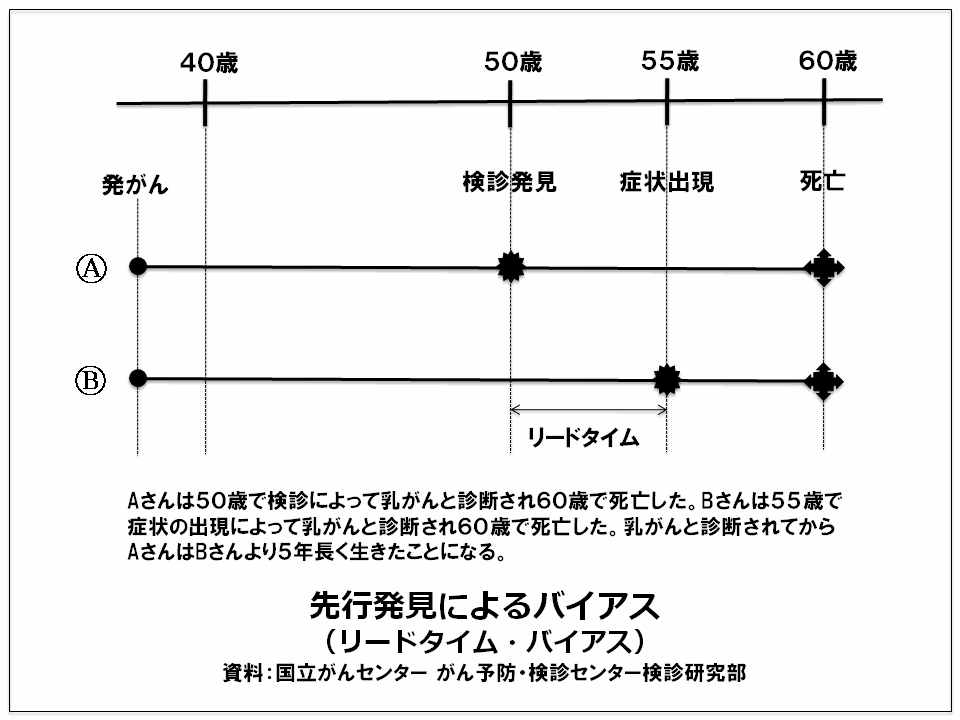
この図を用いて「先行発見によるバイアス」を説明する。AさんとBさんにほぼ同じころ乳がんが発生した。Aさんは50歳のときに検診でがんが発見され、Bさんは55歳のときに症状が現れて乳がんと診断された。二人はともに60歳で乳がんによって死亡した。乳がんと診断されてからAさんはBさんより5年長く生きたことになる(X=5)が、2人の生きた総年数は同じである。それどころか、検診でがんが早く発見されたために、AさんはBさんより5年も長く乳がんと闘わなければならなかったという言い方もできる。
乳がんの過剰診断と過剰治療
乳がん検診には、行政が地域住民を対象にして対策型検診と個人が任意で受ける人間ドック型検診(任意型検診)がある。いずれの検診でも、最初に行われる検査(スクリーニング検査:視診・触診・超音波・マンモグラフィ)で「異常(がんの疑い)あり」と判定されると、「要精密検査」という通知が来る。
通知をもらって医療機関を訪ねると、乳房のMRI(マンモMRI)・CTなどの画像検査や病理検査(細胞診・組織診)が行われる。がんであるかないかを決めるのは病理専門医(あるいは細胞検査士)の仕事である。病理医は、組織の薄切片を顕微鏡で見て、細胞の顔つきががん細胞に似ている、異形の細胞が周辺に浸潤しているなどの変化があると「がん(悪性)」という判定を下す。乳がん治療医は病理医の診断を受けてさらに検査を重ね、病巣の大きさと広がり、周辺のリンパ節への転移のあるなし、遠隔臓器への転移のあるなしなどから病期を判断して治療方針を決める。
病理医は、がんの経過を観察しているわけではなく、ある一時点での細胞の顔つき(核の大きさや染色性)と振る舞い(浸潤の有無)から「悪性」か「良性」か、悪性だとしたらどの程度の悪(わる)かという診断を行っているだけで、その患者のがんが上述のウェルチの分類でいうA〜Dのいずれの経過をたどるか判断する立場にない。病理医はあくまで細胞の面構えと態度から犯人(悪性)かどうかを割り出しているに過ぎない。それなのに、病理診断は現代のがん医療では絶対である。臨床医(治療医)は病理診断に基づいて、治療の要・不要を決めているからである。
他臓器への転移があれば本物の乳がん(ウェルチのAかB)という判断に間違いはない。しかし、検診で発見される乳がんの中には進行が遅く命に影響のない乳がんもある。治療で100%治るといわれる早期がんである。早期がんといわれる変化はしこり(原発巣)の大きさが2センチ以下で転移のない「非浸潤性の乳がん」である。この「がん」が近藤氏の「がんもどき」あるいは「ウェルチのCかD」なら治療を必要としないが、病理医の「細胞の顔つきが悪い」という診断を知らされると、治療医は判断に迷う。が、迷ったあげくに担当医の多くは治療を勧めるし、患者もその勧めを受け入れる。非浸潤性であっても、「様子を見ましょう」と乳がんの手術を先送りする医師は少数派である。進行性の乳がんを見逃したために患者が死亡してしまったら訴訟になりかねないが、放置してもどうということのない「がん」を取り除いたら「おかげで助かりました」と感謝されることもある。
患者は患者で「顔つきの悪い細胞集団」を取り除くことを望む。「早期だから治るのではないか、様子なんか見ていないで早くすっぱり取り除いてほしい」というのが患者心理である。だから医師も患者も病理検査で「がん」と診断されたら「治療(手術)」を選択することになる。早期発見・早期治療のかけ声によって発見された「ウェルチのCとD」が「がん」と診断されることをがんの「過剰診断」という。がんと診断されればそのほとんどが治療を受ける。本来治療の必要のない「CとD」に対する治療が「過剰治療」である。「過剰診断」の後には「過剰治療」が待ち構えている。
乳がんと前立腺がんの検診には過剰診断が多い
「過剰診断・過剰治療」は、健康な人にがん検診を行うようになって初めて出現した概念である。「過剰診断」は、がんでないにもかかわらず「がん」かも知れないという疑いで精密検査に回される「検診の疑陽性」とは異なる。表現を換えると、検診を受けなかったら生涯にわたって発見されなかったであろう「がん」が、検診によって発見されることを「過剰診断」というのである。
「過剰診断」を別の言い方で説明する。40歳の女性を無作為に2群に分ける。一方は定期的に乳がん検診を受け(検診群)、他方は検診を受けずに(未検診群)生涯を過ごしてもらう。本来、乳がんになる確率は両群で同じだから、最初のうちは検診群で乳がんになる人が多い(リードタイムの早期発見)が、そのうちに未検診群に乳がんが増えて、最終的に乳がんになる人の割合は両群で同じになるはずである。ところが、いつまで経っても検診群の乳がん罹患率は未検診群より高いことが知られている。この差が過剰診断である。つまり、本来なら普通に生涯を送るべき人が、検診を受けたために「がん」と診断されて治療を受けることになるのが「過剰診断・過剰治療」である。
過剰診断はゆっくり進行するがんの検診に多い(レングス・バイアス)。その典型は乳がんと前立腺がんである。スクリーニングにPSA(前立腺特異抗原)検査が用いられる前立腺がんの過剰診断は、マンモグラフィによる乳がんの過剰診断よりさらに多い(図)。

2000年の前立腺がん患者は1万9825人であったが、2010年には6万4934人もの男性が前立腺がんと診断されて治療を受けている(数値は国立がん研究センターのがん対策情報センターが公開している地域がん登録に基づく全国推計値)。なんと、前立腺がんの患者が10年で3倍以上に増えた。PSA検診を受けたために、たくさんの男性が「前立腺がん」と診断されて治療を受けたのである。
乳がん検診(マンモグラフィ)による過剰診断
乳がん検診にはどのくらいの過剰診断がつきまとうのだろうか。デンマークのゲッツェ(Gotzsche PC)は、乳がん検診(マンモグラフィ)が始まる前と始まってからの乳がん罹患率を統計学的に解析して過剰診断率を推定している。それによると、デンマークの検診における乳がんの過剰診断率は33%で、4件の乳がんのうち1件は過剰に診断された乳がんであるという*3。また、イギリス・カナダ・オーストラリア・スウェーデン・ノルウェーの過剰診断率は52%で、検診で発見される乳がんの3件に1件は過剰に診断された乳がんであった*4。ゲッツェによると、検診によって過剰診断された乳がんのほぼ全例が本来必要のない治療(=過剰治療)を受けており、検診が多数の過剰治療を招いているという。つまり、過剰診断=過剰治療である。
*3Jorgensen KJ, Zahl PH, Gotzsche PC. Overdiagnosis in organized mammography screening in Denmark. A comparative study. BMC Womens Health 2009 Dec 22;9:36. doi:10.1186/1472-6874-9-36.
*4Jorgensen KJ, Gotzsche PC. Overdiagnosis in publicly organized mammography screenings: systematic review of incidence trends. BMJ 2009 Jul 9;339:b2587. doi:10.1136/bmj.b2587.
乳がん検診によって乳がん死亡を免れる人もいる。しかし、乳がん検診を受けることによって乳がんと診断され(過剰診断)、本来不要な治療(手術・放射線・ホルモン剤・抗がん剤)を受けることになる人もいる(過剰治療)。その結果、乳がん以外の原因で死亡するリスクが高くなる。つまり、乳がん検診に世間が思っているほどのプラス効果はないのである。今さら現実的ではないが、日本でも乳がん検診を2年ごとに1回律儀に受けている女性と、一度も受けたことがない女性の間で生命のトータルの時間を比べてみたら、検診を受けたら長生きするかどうかがはっきりするだろう。
それだけではない。「マンモグラフィ(マンモ検診)を受けなければ……」と急(せ)かされるだけで、乳がん検診そのものが大きな心的ストレスとなる。「乳がんの疑いがあります。精密検査を受けてください」などと言われたときの心的ショックはさらに大きい。身辺整理を始める人もいるほどである。
要精密検査と言われてもそのほとんどは乳がんではない。検診施設によって異なるが、日本のマンモ検診で精密検査に回される人は5〜10%(10〜20人に1人)、そのうち乳がんと判定されるのは0.3〜0.5%(精検受診者の20〜30人に1人)である(この中に過剰診断が含まれている)。精密検査で「乳がんではありません」と言われると、「これで次の検診まで安心だ」と思う女性もいるだろうが、「もう嫌だ。検診なんか二度と受けるものか」という女性もいる。
PSAによる前立腺がんのスクリーニング
女性の乳がんに匹敵する男性のがんは前立腺がんである。女の子の乳房が膨らみはじめる思春期に、男の子では前立腺が急速に成長する。乳がんと同様に、前立腺がんの芽も思春期にできるが、明らかながんは男性ホルモンの分泌が減少して女性ホルモンが優位になる50歳以上の男性に発生することが多い。
前立腺がんのスクリーニングに血液中のPSA(前立腺特異抗原)の測定が行われている(PSA検診)。PSA濃度が4ng/mLを超えると、検査陽性として経直腸的に針を刺して6〜12カ所の前立腺組織を採取する生検が行われる。PSA検診では生検に伴う合併症(出血・炎症など)や過剰診断の多いことが問題になっている。
米国予防医学作業部会は、2011年10月、前立腺がん死亡率の減少は期待できないとして、健康な男性に対するPSA検診は「勧められない」という勧告案を公表した。作業部会は過剰診断などの不利益が早期発見の利益を上回ると判断したのである。これに対して、アメリカ泌尿器科学会は「作業部会の勧告は前立腺がんに罹患する可能性のある男性に不利益をもたらす」と抗議している。
日本でも同様に、泌尿器科学会が、厚生労働省の「がん検診の適切な方法とその評価法の確立に関する研究」班の「市町村はPSA検診を行うべきではない」とする「有効性評価に基づく前立腺がん検診のガイドライン」(2008年3月)に対して「PSA検診は有効である」と反発している。
コラム PSA検診は勧められない(米国予防医学作業部会)
前立腺特異抗原(PSA:Prostate Specific Antigen)は前立腺でつくられるタンパク質分解酵素で、微量が血液中に検出される。血液のPSA 濃度は1980年代の後半から前立腺がんのスクリーニングに用いられるようになった。
PSA検診の有効性をめぐって長いこと研究と議論が重ねられてきたが、米国予防医学作業部会(USPSTF: United States Preventive Services Task Force)は2011年、「年齢を問わず、健康な男性にPSA検診を行うべきではない」という衝撃的な勧告を行った。
USPSTFとはアメリカ厚生省内の保健医療研究品質庁(AHRQ)が運営する保健医療分野の研究と質の向上に関する独立の専門委員会である。関連する学術研究を精査してがん検診などの予防医療の推奨度を発表している。推奨度は 、A「実施すべきである」、B 「実施するほうがよい」、C「実施しないほうがよい(限られた場合のみ行ってもよい)」、D「実施すべきではない」の4段階である。そのほかに、証拠が不十分で(Insufficient)で推奨度を決定できない(I)という判定がある。
前立腺がんに対するPSA検診の推奨度はDであった。「過剰診断と過剰治療による健康被害ががん死亡の減少という利益を上回る」として「健康な男性には勧められない」という判定であった。USPSTFは、2011年10月に勧告案を公開してパブリックコメントを募り、その意見を反映して2012年5月に最終勧告を行った。USPSTFの勧告は法律のような強制力はないものの医療界に大きな影響を与えている。この勧告の全文*1が、PSA検診支持派の反論*2とともに、世界五大医学雑誌の一つであるアメリカ内科医師会発行のアナルズ・オブ・インターナル・メディシン(Annals of Internal Medicine)の7月17日号に掲載されている。これらの論文は同誌のウェブサイトにPDF形式で公開されている。
日本でも、厚生労働省の「がん検診の適切な方法とその評価法の確立に関する研究」班が2008年、PSA検診後の生検などによる合併症や過剰診断が他のがん検診に比べて多いとして、「PSA検査が死亡率を下げるかどうか科学的な結論が出ていないため、PSA検査を住民検診で行うことは勧められない。任意型検診(人間ドック)では、効果が不明であることと過剰診断などの不利益について適切に説明した上で個人が検査を受けるか受けないかを選択する」という報告書を発表している(推奨度I)。
それなのに、日本の市町村と企業には、陽性者に対する基本方針もなく、PSA検診を実施しているところが多い。さらに、あるマスメディアは「各医療機関で無料のPSA検査を実施します。50歳以上のみなさん、この機会に受診してみませんか?」というキャンペーンを張っている。あまりにも無定見である。
因みに、USPSTFは2009年、乳がんのマンモグラフィ検診(2年に1度)について次のような年齢別の推奨度を発表している*3。75歳以上:I、50歳以上74歳まで:B、40歳以上49歳以下:C(検診を受けるかどうかは個人の責任で決める)。40歳代のマンモグラフィがCとなっているのは、この年齢層の乳腺組織が密であるため偽陽性が多いからである。なお、USPSTFは40歳未満の女性がマンモグラフィ検査を受けることを想定していない。
一方、国立がん研究センターがん予防・検診研究センターが発表した「科学的根拠に基づくがん検診」は次のように述べて40歳〜74歳の女性に毎年マンモグラフィ検査を受けることを推奨している。「日本では40〜74歳を対象として、死亡率減少効果を示す相応な証拠があります。不利益については偽陽性、過剰診断、放射線誘発乳がんの発症の可能性があります。これらの結果から、推奨グレードBとし、対策型検診・任意型検診の実施を勧めます」
*1Moyer VA, on behalf of the U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Prostate Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2012;157:120-135.
*2Catalona WJ, D’Amico AV, Fitzgibbons WF, Kosoko-Lasaki O, Leslie SW, Lynch HT, Moul JW, Rendell MS, Walsh PC. What the U.S. Preventive Services Task Force Missed in Its Prostate Cancer Screening Recommendation. Ann Intern Med. 2012;157:137-139.
*3U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Breast Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2009;151:716-726.
乳がん検診(マンモグラフィ)の戒め
検診は健康な人々に何らかの侵襲を加える行為である。どんな検診であれ、プラスとマイナスが表裏をなしているが、がん検診を勧める人たちは「がんは早期に発見して治療すればほとんど治ります」と利益(プラス)のみを強調してマイナス面に触れることを避けている。ゲッツェは英国医学雑誌(BMJ : British Medical Journal)の電子版で、マンモグラフィの利害得失を次のように述べる*。
健康な2000人の女性が10年間、定期的にマンモグラフィを受けると
・200人の健康な女性が精密検査を受ける(精神的・身体的苦痛を蒙る)
・10人の女性が乳がん患者として必要のない治療(乳房切除など)を受ける
・1人の女性が乳がん死亡を免れる
*Jorgensen KJ, Gotzsche PC. Overdiagnosis in publicly organized mammography screenings: systematic review of incidence trends. BMJ 2009 Jul 9;339:b2587. doi:10.1136/bmj.b2587.
乳がん検診の謳い文句は「女性に最も多いがんは乳がんです。日本女性の20人に1人が乳がんになります。乳がんは比較的性質の良いがんで、早期に発見して適切な治療を受ければほぼ完全に治すことができます。しかし、早く治療しなければ、乳がんがリンパ管あるいは血液を通って骨、肺、肝臓などの臓器へ転移して命にかかわります。このような事態を未然に防ぐために、できるだけ早く乳がんを発見して治療を開始しなければなりません」である。こんな宣伝にのって女性は気軽にマンモグラフィを受ける。「40歳以上の女性が2年に1回」といわれても、20代、30代で検診を受けるひともいれば毎年1回受けるひともいる。もうおわかりだろうが、「乳がんは性質が良い」というのは、検診発見の乳がんには「のんびり屋のおっとり君」が多いということでもある。
がん検診機関は「無症状のうちに検診を受ければ早期に乳がんが発見され、その段階で治療すれば治療の経過は良好です」と謳って、検診のマイナス面に全く触れない。プラス(利益)を強調してマイナス(不利益)を隠すのは、客(検診参加者)を増やしたいという思いが強いからだろう。健康な女性が乳がん検診を受けるときは、将来の乳がん死亡が避けられるかも知れないという利益がある一方、不要な治療を受けるという不利益を被る可能性があることをくり返して強調しておきたい。前に述べたゲッツェの「乳がん患者の3〜4人に1人は過剰診断」という数値の当否は別にして、乳がん検診の最大の問題点が「過剰診断」であることは心ある研究者の共通認識である。
乳房に異常を感じてかかりつけのお医者さんに相談したとする。普通の医師は、その心理状況からして、間違いなく精密検査を勧める。専門医にがんではないというお墨付きをもらえば「ああ良かった」と患者は安心する。がんと診断されても「おかげで早期に発見できた」と医師に感謝する。一方、精密検査を勧めないと「もしかすると早期発見の機会を逃すのではないか」と医師の評価が下がる。その後患者が乳がんにでもなったら「心配して相談したのに、あの先生のために早期に治療する機会を失った」と医師は恨まれる。死亡するようなことがあったら訴えられかねない。
医師というプロフェッショナルは古来、苦痛を訴える人に手を差しのべてきた。それなのに最近は、健康な人にエックス線を浴びせるがん検診(肺がん・胃がん・乳がん)を勧める医師がいる。健康な人を傷つける行為は医師の本分にもとる。医の倫理の第一は「健康な人を傷つけない」ことなのだから。医師は、検診を業(ビジネス)とする者たちの一方的な宣伝ではなく、がん検診のマイナス面も自分の患者に伝えてほしい。
2009(平成21)年度に厚生労働省のがん検診受診向上指導事業として行われた「がん検診受診向上アドバイサリーパネル委員会」の『かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック』(2010年3月)に「がん検診の不利益」というコラムが掲載されている。このハンドブックは医師向けで、一般の人が目にする機会は少ないと思われるので、このコラムの全文を紹介する(このハンドブックはネットで公開されている)。
がん検診の不利益
がん検診の最大の利益は、早期発見によりがん死亡率が減少することです。個人に言い換えれば、がんの死亡リスクが減少するということになります。しかし、この恩恵はがん検診を受診する人にあまねく行き渡るわけではありません。がん検診には利益だけでなく、重大な不利益もあります。むしろ、この不利益こそが、受診者に広く行き渡る可能性があります。がん検診は、対象となる臓器や検査の種類により、不利益の種類は異なります。しかし、どのようながん検診にも共通し、多くの人が遭遇する可能性のあるものは「疑陰性」、「疑陽性」と「過剰診断」です。
「疑陰性」とは、がんがあるにもかかわらず、正しく診断されないことです。いわゆる見逃し例です。がん検診に限らず、検査の精度は100%ではありません。進行がんで発見された場合には、生命予後にも影響があります。しかし、早期の段階であれば、初回の検診でがんが診断できなかった場合でも、適切な間隔で検診を受け続けることにより、がんによる死亡を回避する可能性は高くなります。このため、がん検診は単発の受診ではなく、適切な間隔で受け続けることが必要です。
「疑陽性」とは、がんがないにもかかわらず、がんがあるかも知れないと診断されることです。具体的には、最初に受けたがん検診の結果、精密検査が必要と判断されることです。精密検査が必要となるのは、がんの疑いを除外するためと、がんであることを確かめるための2つの意味があります。こうした結果が出た場合には、専門の医療機関を受診し、精密検査を受ける必要があります。実は、要精密検査とされた場合でも、真にがんと判断される(陽性反応適中度)のは、胃がん検診では1・5%、最も可能性のある子宮頸がん検診でも4・9%に過ぎません。むしろ、多くの人々が「がんではなかった」という結果を受け取ることになります。受診者は、精密検査のための身体的な負担や追加費用だけでなく、その結果が出るまでには精神的な不安を持つことも避けられません。
もう一つの重大な不利益に、「過剰診断」があります。がん検診で発見されるがんの中には、本来そのがんが進展して死亡に至るという経過を取らない、生命予後に関係のないものが発見される場合があります。こうした「がん」は消えてしまったり、そのままの状況に留まったりするため、生命を脅かすことはありません。また、精度が高いとされる検査で発見される前がん病変も、すべてががんに進展するわけではなく、むしろがんになるのはほんの数%に過ぎません。しかし、実際にがん検診を受けて「がん」として見つかったものについては、多くの場合は通常のがんと同様の診断検査や治療が行われます。診断検査や治療には、経済的だけでなく、身体的・心理的にも大きな負担を伴います。場合によっては、治療による合併症のために、その後の生活に支障をきたすこともあります。早期発見されたがんの中には、一定の過剰診断が含まれていますが、がんの種類や検査法によりその割合は異なります。現在の医療では、どのようながんが進展し、生命予後に影響を及ぼすかはわかっていません。
検診でがん患者が増える
日本では、毎年新たに、7万人を超える女性が乳がん治療(手術・放射線・抗がん剤・ホルモン剤)を受けている。がん対策は、本来、がんになる人の数を減らすこと(予防)が最優先なのに、日本の乳がん対策は検診(早期発見・早期治療)にかたよっている。日本女性の検診受診率(20〜30%)は欧米に比べると低い。欧米並み受診率(50〜70%)の達成が政府・医療界・患者団体の合言葉となっている(2007年に策定されたがん対策推進基本計画は乳がん検診の受診率50%以上を数値目標としている)。受診率が高くなったら、日本女性が乳がんの恐怖から逃れられると本気で考えているのだろうか。
検診事業はがん患者を掘り起こしている。事業の拡大によって、過剰診断・過剰治療がますます増える。女性は何度でも、乳がんが発見されるまで検診を受けなければならない。乳がんになってはじめて乳がん検診のくびきから解放される。何度でも言うが、乳がん検診によって女性の乳がんが減るわけではない。根本的な対策(=予防)が必要である。
日本で乳がんが実質的に増えていることは間違いないが、この乳がん患者の増加の一部が乳がん検診に伴う過剰診断によるものであることを忘れてはならない。検診技術が精密になって微小な病変が発見されるようになればなるほど過剰診断が増える。乳がんの年齢別罹患率を眺めると、2010年の罹患率は2000年に比べて尋常とは思われないほどに増えた。検診、検診と叫ばれるがために、多数の女性が乳がんと診断されて治療を受けたのである。その中に相当数の過剰診断の乳がんがあったものと想定されるが、データ不足のため日本における過剰診断の割合は不明である。
コラム がん検診パラドックス
PSAやマンモグラフィに過剰診断が多いのは、何ら症状を呈することなく、健康な人の前立腺と乳腺にがん細胞の塊(かたまり)が潜んでいるからである。
前立腺はクルミ大(20グラム程度)の臓器である。小さな器官だから端から端まで隈なく調べることができる。交通事故などで死亡した人の前立腺を顕微鏡で精査したところ、60〜70歳では60〜70%の人にがん細胞が見つかった*1。驚くべきことに、20代の青年の前立腺にも、ほぼ10%にがん細胞が発見された(図)。
つまり、手を尽くして捜せば30代の30%、40代の40%、50代の50%にがん細胞が見つかるのである。PSA検診を受けると、この静かに眠っている細胞の塊が見つかって「前立腺がん」と命名される。その大部分はウェルチのCやDである。
乳腺についても、剖検で乳がんを捜した研究が7つあって、40〜50代の女性の7〜39%に乳がんが見つかっている*2。研究によってこんなに差があるのは、病理医の判断基準が異なることにもよるが、研究ごとに調査の精密性が異なるからである。乳房当たり200の切片を調べている研究もあれば、10切片しか調べていない研究もある。
有名人が「早期発見で助かった。検診を受けましょう」とテレビなどで宣伝すると、過剰診断の多い検査ほど人気が出て、過剰診断がますます増える。この現象は「がん検診パラドックス」と呼ばれている。
*1Sandhu GS, Andriole GL. Overdiagnosis of prostate cancer. Journal of the National Cancer Institute Monographs 2012; 45:146-152.
*2Welch HG, Black WC. Using autopsy series to estimate the disease "reservoir" for ductal carcinoma in situ of the breast: how much more breast cancer can we find? Ann Intern Med 1997; 127:1023-1028.
なぜ北欧の乳がん死亡は減ったのか
ここで、マンモグラフィが乳がん死亡を本当に減らすのかという根源的な問題に触れておく。1990年頃から欧米で乳がん死亡が減りはじめた。同じ頃欧米で、マンモグラフィによる乳がん検診が推進されていた。そのため、この乳がん死亡の減少こそ、マンモグラフィの有効性を示す何よりの証拠だと受けとられてきた。
2011年、British Medical Journal(BMJ、英国医学雑誌)にオンラインで発表された論文*1は、ヨーロッパの乳がん死亡がマンモグラフィの導入以前から減少傾向にあったこと、この減少傾向がマンモグラフィの導入によって変わらなかったことを明らかにして、欧米における乳がん死亡の減少は検診によるものではないと結論づけている。この論文は、1)国境が接している 2)人口規模と社会経済環境が似ている 3)マンモグラフィの導入時期が異なっている、3対のヨーロッパの国々(北アイルランドとアイルランド共和国、オランダとベルギー、スウェーデンとノルウェー)におけるマンモグラフィの導入と乳がん死亡率の時間的関係を解析したものである(マンモグラフィは北アイルランド、オランダ、スウェーデンで先に始まった)。解析の対象になったいずれの国でも、乳がん死亡の減少がマンモググラフィの導入と関係なく始まっていた。しかも、年齢別に観察すると、検診を受ける機会が比較的少ない40代の女性で乳がん死亡率が最も大きく低下していた。
*1Autier P, Boniol M, Gavin A, Vatten LJ. Breast cancer mortality in neighbouring European countries with different levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of WHO mortality database. BMJ 2011; 343:d4411. doi: 10.1136/bmj.d4411.
このうち、スカンディナビア半島の東西に隣りあうスウェーデンとノルウェーにおける、マンモグラフィ検診と乳がん死亡の関係について述べる(図)

スウェーデンでは1986年からマンモグラフィによる乳がんの組織型検診が実施され、1997年には50〜69歳のすべての女性に検診通知が送られるようになった。一方、ノルウェーでは、スウェーデンにほぼ10年遅れて始まったマンモグラフィ検診が2003年になってはじめて全国的に普及した。因みに、1995〜99年の受診率はスウェーデンでは80%に達していたが、ノルウェーでは30%以下であった。スウェーデンとノルウェーにおけるマンモグラフィ検診導入の時間差は平均12年である。
スウェーデンでは1987〜89年から2004〜06年にかけて乳がんの年齢調整死亡率(ヨーロッパ標準人口10万対)が25.6から21.5に下がった。一方、ノルウェーでも同じ期間に27.4から21.5へと下がっている。スウェーデンにおける乳がん死亡の減少傾向は、上図で明らかなように、乳がん検診が全国的に実施される前の1980年から始まっている。同様にノルウェーでも、乳がん検診が全域で普及する前の1996年から死亡率の低下が始まっている。つまり、スウェーデンでもノルウェーでも、乳がん死亡の減少がマンモグラフィ検診とは関係なく起こっているのである。
この論文の著者オウティエ(Autier P)は、北欧で乳がん死亡が減ったのは新規乳がん治療薬(ホルモン剤、分子標的薬)の開発によるものであると推定している。しかし、これはおかしい。新しい治療薬によって乳がんの死亡が少なくなるのなら、日本でも乳がんの死亡が減ってしかるべきではないか。日本では乳がん死亡が減らないどころか増え続けている。日本の乳がんの治療技術は北欧に比べて劣っているのだろうか。そんなことはあるまい。北欧で乳がん死亡率が下がっているのは検診(マンモグラフィ)や治療(新規薬剤)によるものではなく、他の要因が働いている。
何が北欧の乳がん死亡を減少させたのか。実は1970年代に、北欧の人々の食生活に大きな変化が起った。牛乳やバターの消費量が大幅に減ったのである。
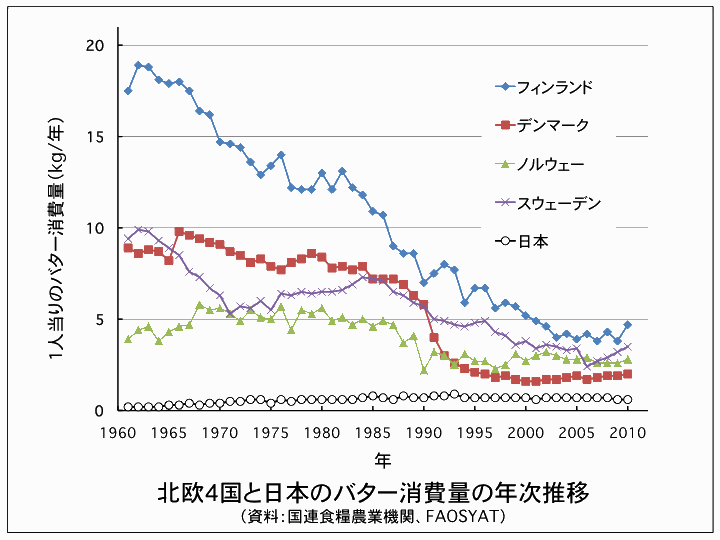
たとえば、国連食糧農業機関(FAO)の資料によると、スウェーデンのバター消費量は1970〜79年には年間1人当たり平均6.7キログラムであったが、2000〜07年には3.3キログラムと半減している(上図)。ノルウェー、デンマーク、フィンランドのバター消費量も同様である。とくに心筋梗塞が世界一と高名(?)を博していたフィンランドでの減少が著しい。さらにいずれの国でもバターの減少に加えて牛乳の飲用が減った。飽和脂肪酸の多い動物脂肪が北欧に多い心筋梗塞(冠動脈硬化)の原因とみなされるようになって、北欧人が牛乳やバターを控えるようになったのである。
北欧の人々が牛乳やバターを減らしたことが、北欧における乳がんの死亡減少の背景にあるのではないか。日本人のバター消費量は北欧に比べて少ないが、上図のように減少することなく推移している。牛乳消費量はデンマークを追い越している(下図)。日本女性の乳がん死亡率は欧米に比べると低いが、乳がん死亡が一向に減らない理由がおわかりいただけるだろう。
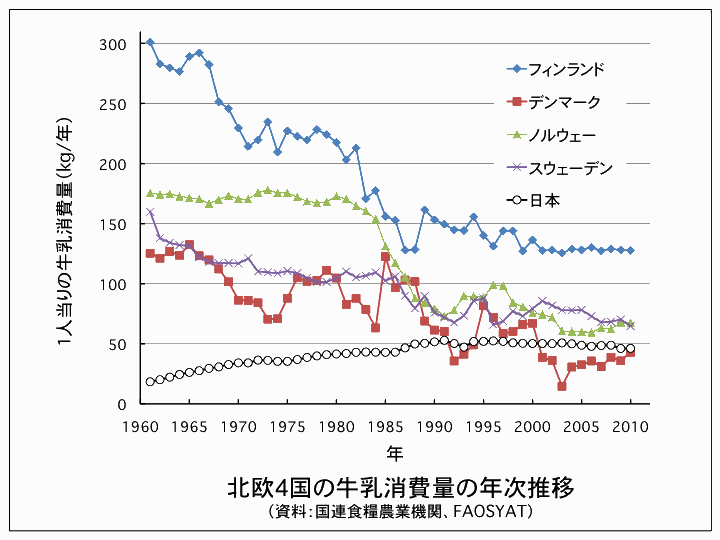
コラム デンマークの脂肪税は牛乳税?
デンマーク政府は2011年10月1日、国民の健康を増進するという理由で、バターなどの飽和脂肪酸を多く含む食品に対する課税を始めた。飽和脂肪酸を2.3%以上含むバター、チーズ、加工食品などが課税対象となり、飽和脂肪1キログラムあたり16クローネ(約220円)の税金が徴収されることになった。高脂肪食品への課税は世界で初の試みであった。
飽和脂肪酸の多い食品は肥満の要因であり、動脈硬化の原因となる悪玉コレステロールを増やすとされている。課税による販売価格の上昇が国民の健康増進につながるというのが脂肪税創設の狙いであった。
デンマークは酪農王国である。当初から脂肪税の導入には業界の強い反対があった。当然、消費者からも新税反対の声が上がっていた。長い年月をかけて築かれてきた嗜好が簡単に変わることはない。実際、課税対象となった食品の売り上げは一時的に減少したものの数か月で元の水準にもどった。そのため、健康増進を口実にした財源確保ではないかという批判が日増しに強くなった。
そして、2012年11月11日、デンマーク政府は2013年の国家予算の策定にあたって「脂肪税の廃止」を発表した。世界で初めての制度として注目された脂肪税は、およそ1年間という短期間で廃止されることになった。
デンマークでの脂肪税の導入に先立って、EUでは飽和脂肪酸の含有量の食品表示が義務化されていた。脂肪税は早々と撤退したが、この新税は「バターはあまりよい食品ではない」という疑念を改めてEU諸国の人々にもたらすことになった。
ところで、デンマークの脂肪税で課税対象となったのは「2.3%以上の飽和脂肪酸を含む食品」であった。2.5%や3%でなく、2.3%という微妙な数字が面白い。牛乳脂肪の60%は飽和脂肪酸である。デンマークや日本で搾られているホルスタイン牛乳の乳脂肪は3.8%で、牛乳の飽和脂肪酸は2.3%である。デンマークは牛乳を課税対象とするために2.3%という数字を選んだのではあるまいか。
がん検診はビジネス
若い女性に好発する乳がんは市場経済では格好の「メシのタネ」である。昨今は乳がん産業(ビジネス)が隆盛を極めている(ロレッタ・シュワルツ=ノーベル『Poisoned Nation』、東出顕子訳『アメリカの毒を食らう人たちー自閉症、先天異常、乳癌がなぜ急増しているか』東洋経済新報社、2008年5月)。乳がんビジネスの対象(お客さま)は30代〜40代の若い女性層である。
牛乳をたくさん飲み、ケーキ・アイスクリームをたくさん食べてくれれば、酪農・乳製品メーカーが喜ぶ。その結果、乳がんが増える。乳がん検診は検診業界の重要な収入源であり、医療機器メーカーの収益につながる。患者の治療で医療・製薬業界が潤う。死ねば・・・。だから、日本人の乳・乳製品の消費量増大は単に乳業・酪農業界だけでなく、日本経済全体に少なからぬ波及効果をもたらす。日本人が乳・乳製品を止めて乳がんが減ったら、日本経済は縮小してしまうのである。市場経済では喜怒哀楽のすべてが経済成長の糧(かて)となる。
大部分の日本人は1945(昭和20)年前までの長い歴史を乳・乳製品と無縁で過ごしてきた。それなのに、ただ欧米人が食べているというだけで、日本人はミルクとヨーグルトほど健康によいものはないと思い込んでしまった。さらに栄養学者は「背が高くならない」「骨粗鬆症になる」と脅迫まがいに乳・乳製品を勧奨した。美味しいから食べるというのは構わないが、健康のために乳・乳製品などを食べてはいけない。ミルクという白い液体は未熟で生まれた哺乳類の子どもを大きくするために母親が分泌する成長促進剤である。赤ん坊だけでなく、腫瘍も生長する。